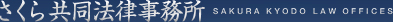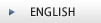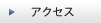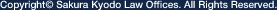竹内 康二(Koji Takeuchi)
昭和19年9月3日生
【経歴】
| 昭和38年6月 | ニューヨーク州ロチェスターブライトン高校卒業 |
| 昭和39年3月 | 愛知県立旭丘高校卒業 |
| 昭和39年4月 | 東京大学教養学部入学 |
| 昭和39年5月 | 通訳案内業試験合格 |
| 昭和42年7月 | 国家公務員上級試験合格 |
| 昭和42年9月 | 司法試験合格 |
| 昭和43年3月 | 東京大学法学部卒業 |
| 昭和45年4月 | 司法修習を修了 |
| 昭和45年4月 | 東京弁護士会登録、直ちに松尾翼(現在の松尾総合)法律事務所弁護士として勤務 |
| 昭和47年4月 | 河合・竹内法律事務所開設 |
| 昭和52年4月 | 法政大学法学部講師(以後、破産法講座及び民事訴訟法二部講座を隔年担当) |
| 昭和54年4月 | 河合・竹内・西村法律事務所と改称 |
| 昭和57年8月 | ニューヨーク市コロンビア大学ロースクール大学院に留学 |
| 昭和58年5月 | 同大学ロースクールから修士号(LL.M.)を受ける その後、アトランタのハート・リチャードソン・ガーナー・トッド・ケイデンヘッド法律事務所弁護士を経験 |
| 昭和58年12月 | 帰国 この間、昭和58年3月、アメリカン・バー・アソシェーション(A.B.A)主催の ニューヨーク・ウォルドルフ・アストリアで開かれた国際破産及び国際債務整理セミナーのパネルのメンバーとして講演。 |
| 昭和61年2月 | ニューヨーク州司法試験合格 |
| 昭和61年6月 | ニューヨーク州裁判所法曹登録 アメリカン・バー・アソーシエーション(A.B.A)登録 |
| 平成3年6月 | さくら共同法律事務所と改称 |
| 平成9年4月 | 学習院大学法学部講師(破産法担当) |
| 平成12年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師(倒産法) |
| 平成16年4月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(倒産法) |
【著書・論文】
| 1. | 「国際破産への試論」 (法学志林76巻2号) |
|
| 2. | 「継続的商品売買取引における売掛金残額請求の特定方法」 (NBL88-46 商事法務) |
|
| 3. | 「破産と仮登記担保」 (『破産法一実務と理論の問題点』経済法令研究会) |
|
| 4. | 「破産と取戻権」 (『破産法一実務と理論の問題点』経済法令研究会) |
|
| 5. | 「代物弁済の否認」 (堀内仁編金融法務解釈事典第5章株式会社ぎょうせい) |
|
| 6. | 「相殺権行使の否認」 (堀内仁編金融法務解釈事典第5章株式会社ぎょうせい) |
|
| 7. | 「和議の効力」 (『和議・会社整理・特別清算−実務と理論の問題点』経済法令研究会) |
|
| 8. | 「監査委員の職務権限」 (『和議・会社整理・特別清算−実務と理論の問題点』経済法令研究会) |
|
| 9. | 「和議と取戻権」 (『和議・会社整理・特別清算−実務と理論の問題点』経済法令研究会) |
|
| 10. | 「信託を利用した債務整理の実務報告(上)(下)」 (NBL246-26,249-39 商事法務) |
|
| 11. | 「私的整理と法律」 (『私的整理−実務と理論の問題点』経済法令研究会) |
|
| 12. | 「日本における債権者の権利と破産法」(英文) (アメリカン・バー・アソシエーション・ナショナル・インスティテュート) |
|
| 13. | 「アメリカの開示制度と日本への影響」 (ジュリスト1984年11月1日号 有斐閣) |
|
| 14. | 「私的整理手続の構造」 (『裁判会社訴訟・会社更生法』青林書院新社) |
|
| 15. | 「手形の譲渡担保」 (『新版会社更生法』経済法令研究会) |
|
| 16. | 「仮登記担保」 (『新版会社更生法』経済法令研究会) |
|
| 17. | 「国際的取引と債権保全」 (『現代契約法大系9』 有斐閣) |
|
| 18. | 「国際倒産処理」 (『現代倒産法入門』法律文化社) |
|
| 19. | 「倒産処理法の改正問題」 (『転換期の日本法制』ジュリスト1987年1月1-15日号 有斐閣) |
|
| 20. | 「実例からみた国際倒産の法的諸問題〔上〕〔中〕〔下〕」 (債権管理1988年第7号〜9号) |
|
| 21. | 「国際取引と債権管理回収実務の基礎知識」(債権管理1988年第7号〜10号) | |
| 1)アメリカからの国際的な在庫の引揚げ | ||
| 2)アメリカ集合動産担保に対する動産売買代金担保権の優先−我が国最高裁の新判例との対照 | ||
| 3)動産売買代金担保権の行使とアメリカ連邦倒産手続 | ||
| 4)動産売買代金担保権のアメリカ連邦倒産手続との攻防 | ||
| 22. | 「国際倒産法の立法論的検討・第2部国際倒産法をめぐる国際的動向−その新たな始まりと現状」 (金融法研究資料編(4)1988年9月10日号) |
|
| 23. | 「国際倒産処理の現状と課題」 (自由と正義1988年12月号) |
|
| 24. | Questionnaire on Creditors' Rights Against Business Debtors, International Loan Workouts and Bankruptcies (Butterworth Legal Publishers 1989) | |
| 25. | 「国際倒産法の立法論的検討」 (金融法学会シンポジウム報告・金融研究1989年第5号) |
|
| 26. | 「不動産の処分と詐害行為」 (『現代民事裁判の課題−不動産取引編』新日本法規出版) |
|
| 27. | 「ジュリスト書評−貝瀬幸雄著『国際倒産法序説』」 (ジュリスト1990年2月1日号 有斐閣) |
|
| 28. | 「国際動産売買の諸問題」 (『現代民事裁判の課題−動産取引編』新日本法規出版) |
|
| 29. | 「更生計画における公正衡平(1)−親会社の権利」 (別冊ジュリストNo.106 1990年2月号 有斐閣) |
|
| 30. | 「国際倒産法」 (共著)(商事法務研究会) |
|
| 31. | 「国際金融取引と倒産法」 (ジュリストNo.971 1991年1月1-15日号 有斐閣) |
|
| 32. | 「交渉者としての法律家」『法交渉学入門』 (商事法務研究会) |
|
| 33. | 「不動産保有会社の倒産処理−バブル経済の破綻−」 (東京弁護士会平成3年度秋季弁護士研修講座) |
|
| 34. | 「民事訴訟法施行100年記念国際シンポジウム『国際化時代における民事司法』:第3テーマ「国際倒産」 (民事訴訟法学会) |
|
| 35. | Cross-Border Bankruptcy Japanese Report, The International Symposium on Civil Justice in the Era of Globalization (Shinzan Books, 1992) | |
| 36. | Japanese Insolvency Law, Multinational Commercial Insolvency (American Bar Association 1993) | |
| 37. | 「属地主義と普及主義」 (『倒産処理・清算の法律相談I』第4章国際倒産1994年) |
|
| 38. | 「管財人の権限」 (『倒産処理・清算の法律相談I』第4章国際倒産1994年) |
|
| 39. | Treatment of International Insolvency Issues in Japan, in Current Issue in Cross-Border Insolvency and Reorganization 69 (Leonard and Besant eds., 1994) | |
| 40. | Issues in Concurrent Insolvency Jurisdiction:Comments on the Papers by Grierson and Flaschen-Silverman ,Current Developments in International and Comparative Corporate Insolvency Law (Ziegel ed, 1994) | |
| 41. | 「国際倒産法の構築と展望」 (成文堂1994年) |
|
| 42. | 「先物外国為替取引・スワップ取引と倒産法 −取引所の相場のある商品売買・交互計算の規定をめぐって−」 (判例タイムズ830号 1994年) |
|
| 43. | 「倒産判例ガイド」 (共著 有斐閣 1996年) |
|
| 44. | 「国際訴訟のQ&A具体的紛争とその解決策」 (共著 商事法務研究会 1996年) |
|
| 45. | 「債権管理・回収モデル文例書式集」 (共著新日本法規出版1996年) |
|
| 46. | 「ゴネ得・ヤリ得のそろばん勘定と懲罰的賠償−怖いのは刑事裁判だけでいいのか(その1)」 (金融・商事判例No.996 1996年8月1日号) |
|
| 47. | 「ダシ得・ダシ惜シミ得のそろばん勘定と証拠法則−怖いのは刑事裁判だけでいいのか(その2)」 (金融・商事判例No.1002 1996年11月1日号) |
|
| 48. | 「倒産実体法の立法論的研究(五)」 (民商法雑誌115巻・3号) |
|
| 49. | 「擦り寄り得と、退き得のそろばん勘定と、法曹倫理−怖いのは刑事裁判だけでいいのか(その3)」 (金融・商事判例No.1009 1997年2月1日号) |
|
| 50. | 「裁判のための税務証拠資料の揃え方」 (税経通信 1997年2月臨時増刊号) |
|
| 51. | 「法規と倫理に支えられたこれからの民事証拠の収集・選別・取調べ−怖いのは刑事裁判だけでいいのか(その4・完)」 (金融・商事判例No.1015 1997年5月1日号) |
|
| 52. | Subject Outline For Japan, Worldwide Reorganization and Restructuring,(American Bankruptcy Institute, West Law, West Publishing 1997) | |
| 53. | 「最新事例研究②デリバティブ−大和銀行・住友商事・ヤクルト本社事件を中心に−」 (税経通信1999年1月号) |
|
| 54. | Chapter 11 Insolvency Proceedings, Hattori・Henderson Civil Procedure in Japan - Second Edition (2000) | |
| 55. | 日本民事訴訟法学会50周年記念シンポジウム『倒産法改正の方向−新再建型手続を中心として一』(3)担保権の倒産法における処遇「Ⅱ倒産手続における担保権の実体的な統制の可否をめぐって」 (民事訴訟法雑誌46号) |
|
| 56. | 「私的整理のあらたな展開とその比較法的検討−会社法と倒産法による裁判外での効率高い協調へ−」 (『新堂幸司先生古稀祝賀民事訴訟法理論の新たな構築』(下) 有斐閣) |
|
| 57. | 「併行倒産」 (新・裁判実務大系『国際民事訴訟法(財産法関係)』共著 青林書院) |
|
| 58. | 国際倒産法シンポジウム「外国倒産手続の承認」 (2001.11月 ソウル) |
|
| 59. | 「倒産内外を通じた動態的担保試論−人的財産担保の変動をめぐって−」 (『竹下守夫先生古希祝賀権利実現過程の基本構造』 有斐閣 2002年) |
|
| 60. | Liabilities to Third Parties on Issues of Securities Japanese Report, (Originally prepared as a paper given at the Conference of the International Bar Association, Durban 2002) | |
| 61. | Japan has Revamped its Corporate Insolvency System by Creating New Procedural Rules and Substantive Provisions, (Originally prepared as a paper given at the Conference of LAWASIA, Tokyo 2003) | |
| 62. | 「アメリカ統一商事法典改正第9章入門 (Uniform Commercial Code-Secured Transactions, Revised Article 9)」 (2010年3月25日国際商事法研究会) |
|
| 63. | 「市場の相場がある商品取引契約」 (「倒産処理法制の理論と実務 The Theory and Practice of Insolvency Law」別冊 金融・商事判例) |
|
| 64. | 「高度ファイナンス取引:「倒産法の尽きた」ところにある契約法を考える-証券化、デリバティブ取引、ルポ取引などをめぐって-」 (「遠藤光男元最高裁判所判事喜寿記念文集」株式会社ぎょうせい 2007年) |
|
| 65. | 「双務契約再考−売主の本旨履行請求の要件事実と双方未履行解除をめぐって−」 (「小島武司先生古稀祝賀 民事司法の法理と政策 上巻」株式会社商事法務 2008年) |
|
| 66. | Sale of Business in Bankruptcy Context in Japan, (Originally prepared as a paper given at the 11th Annual International Insolvency Conference, NY 2011) | |
| 67. | 米国における債権保全のテクニック (2012年3月14日 米国における債権管理実務セミナー) |
|
| 68. | 「破産法大系第II巻 -破産実体法-」(共同執筆、平成27年2月・青林書院) 「第5章 11 破産管財人の選択権」 執筆 |
|
| 69. | 集合動産担保権ならびに集合債権担保権 (『倒産実体法の契約処理』第11章抜刷、商事法務2011年) |
|
| 70. | 倒産内外を通じた動態的担保試論-人的財産担保の変動をめぐって (『倒産実体法の契約処理』第12章抜刷、商事法務2011年) |
【学会】
| ■民事訴訟法学会会員 |
| ■ABA, Section of Business Law |
| ■ABA, Section of Taxation |
| ■ABA, Section of Patent, Trademark, and Copyright Law |
【取扱事件・経験】
| < 集団的債務処理事件に関する経験 > | |
| 1.会社更生事件 | |
| (1) | 株式会社松田製作所(法律顧問) 浦和地方裁判所昭和49年(ミ)第1号 |
| (2) | 東和化学工業株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所昭和50年(ミ)第12号 |
| (3) | 光陽精機株式会社(法律顧問) 千葉地方裁判所昭和53年(ミ)第1号 |
| (4) | ベルテック株式会社(法律顧問) 東京地方裁判所昭和53年(ミ)第9号 |
| (5) | ベルテック商事株式会社(法律顧問) 同裁判所同年(ミ)第10号 |
| (6) | 新明興産業株式会社(管財人) 水戸地方裁判所下妻支部昭和53年(ミ)第1号 |
| (7) | リッカー株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所昭和59年(ミ)第7号 |
| (8) | リッカー不動産株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所昭和59年(ミ)第8号 |
| (9) | 総武通商株式会社(被申立代理人) 東京地方裁判所昭和60年(ミ)第2号 |
| (10) | 株式会社太平洋クラブ(申立代理人) 東京地方裁判所昭和60年(ミ)第4号 |
| (11) | オート株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所昭和61年(ミ)第5号 |
| (12) | 株式会社クロス・カルチャー事業団(申立代理人) 東京地方裁判所平成元年(ミ)第7号 |
| (13) | 株式会社阿貝ゴルフクラブ(債権者申立代理人) 東京地方裁判所平成15年(ミ)第10号 |
| 2.会社整理事件 | |
| (1) | 三王工業株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所昭和51年(ヒ)第1022号 |
| (2) | 株式会社ハマデン(申立代理人) 静岡地方裁判所浜松支部昭和51年(ヒ)第12号 |
| (3) | 大友食品株式会社(申立代理人) 名古屋地方裁判所昭和57年(ヒ)第8号 |
| (4) | 足立産業株式会社(被申立代理人) 浦和地方裁判所昭和60年(ヒ)第20号 |
| 3.破産管財業務 | |
| (1) | 三栄雑貨株式会社管財人 東京地方裁判所昭和53年(フ)第203号 |
| (2) | 加藤金物株式会社管財人 同裁判所昭和53年(フ)第170号 |
| (3) | 日本興商株式会社管財人 同裁判所昭和54年(フ)第111号 |
| (4) | 株式会社ヤガイ管財人 水戸地方裁判所下妻支部昭和54年(フ)第4号 |
| (5) | 後藤建設工業株式会社管財人 同裁判所昭和55年(フ)第2号 |
| (6) | 日本瀝青工業株式会社管財人 東京地方裁判所昭和61年(フ)第538号 |
| (7) | 岩崎電工株式会社管財人 同裁判所平成2年(フ)第813号 |
| (8) | 株式会社アーバン外2社管財人 名古屋地方裁判所平成3年(フ)第87号〜89号 |
| 4.和議事件 | |
| (1) | 新井機械製作所(申立代理人) 東京地方裁判所昭和49年(コ)第13号 |
| (2) | 虫プロ商事株式会社(強制和議申立代理人) 東京地方裁判所昭和48年(フ)第179号 |
| (3) | 株式会社岩崎製作所(申立代理人) 横浜地方裁判所川崎支部昭和56年(コ)第1号 |
| (4) | 株式会社ホテルリッチ外7社(申立代理人) 東京地方裁判所昭和59年(コ)第18号外7件 |
| (5) | 岩崎電工株式会社(整理委員) 東京地方裁判所平成2年(コ)第1号 |
| (6) | 和光交易株式会社(整理委員) 東京地方裁判所平成2年(コ)第7号 |
| (7) | 株式会社イマギイレ(申立代理人) 浦和地方裁判所平成5年(コ)第2号 |
| 5.民事再生事件 | |
| (1) | 豊和工業株式会社(申立代理人) さいたま地方裁判所平成14年(再)第2号 |
| (2) | 田安商事株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所平成15年(再)第267号 |
| (3) | 大成礦油株式会社(申立代理人) 東京地方裁判所平成15年(再)第268号 |
| 6.清算・特別清算 | |
| (1) | シェクスピア株式会社(清算人代理人) |
| (2) | 株式会社リースセンター(特別清算人代理人) 浦和地方裁判所平成6年(ヒ)第111号 |
| (3) | 株式会社花楽(清算人代理人) |
| (4) | 有限会社誠和工事 |
| 7.私的整理事件30数件 | |
| < 特記事件 > |
| 1. | ダグラス・グラマン事件において有森国雄証人の随伴者として衆議院予算委員会に出頭。証言並びにその拒絶につき指導をする。 |
| 2. | 著名刑事事件を含めて無罪判決の確定した依頼者数9件。 |
| 3. | 弁護を担当した刑事事件(名古屋地方裁判所 平成29年(わ)第427号 不正競争防止法違反被告事件 令和4年3月18日判決)が5年の審理の後、無罪判決となりました。 世界的著名企業の技術に関する営業秘密を役員が口頭開示をしたという事案でした。 第1審無罪判決は、検察の控訴がなく確定しました。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/091195_hanrei.pdf |