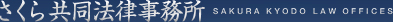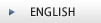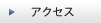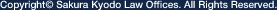相続の基本
我々弁護士にとって、相続問題はよく相談を受ける分野であり、また多くの紛争処理の依頼を受ける分野です。
従って、ネットローでも、今後相続関連の解説記事を掲載していきたいと考えていますので、まずは、「相続の基本」について解説したいと思います。
「相続欠格」、「相続人の廃除」、「特別受益者制度」、「寄与分」、「相続の放棄」、「限定承認」などについても解説しています。
1 相続とは
相続とは、死亡などの相続原因が発生した場合に、被相続人から相続人に財産上の地位が移転する制度です。もう少し平たく言えば、私たち自然人(法人ではない人間)が死亡することによって、その自然人に帰属していたい財産や権利・義務が、子供や妻などの他の自然人によって包括的に承継される制度です。
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
2 相続人とは
被相続人の財産上の地位を承継する人のことを「相続人」といい、相続される財産や権利・義務の主体であった人を「被相続人」といいます。相続人となる人は、被相続人の子、配偶者、直系尊属及び兄弟姉妹です。胎児も、被相続人の子として相続する資格があります。
なお、内縁の妻は、内縁の夫の相続人にはなりません。内縁の妻に遺産を残すには、遺言書を書いて遺贈(遺言のよる贈与)をするか、死因贈与契約を締結しておく必要があります。
相続の順位は、被相続人の子が第1順位、(子がいない場合)被相続人の親などの直系尊属が第2順位、(子も直系尊属もいない場合)被相続人の兄弟姉妹が第3順位となります。被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記相続人と同順位になります。例えば、夫が死亡し、子と妻がいる場合は、子と妻は同順位で相続人となります。
3 代襲相続とは
相続の開始以前に被相続人の子もしくは兄弟姉妹が死亡しているけれど(したがって相続人ではない。)、仮に生存していればその者が相続人となる場合で、その者の子がいる場合には、その者の子が代わって相続します。これを「代襲相続」といいます。
また、代襲者である相続人の子が死亡している場合は、孫が代わって相続し、これを「再代襲相続」といいます。
4 相続欠格とは
次のような行為を行った者は、相続人としての資格を失います。これを「相続欠格」といいます。
① 故意に被相続人、又は相続に関し先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告訴・告発しなかった者
③ 詐欺・脅迫により、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取消をさせ、又は変更させた者
④ 詐欺・脅迫により、被相続人が③記載の行為をすることを妨げた者
⑤ 遺言書を偽造・変造し、もしくは破棄・隠匿した者
なお、遺言書ではなく、相続財産を隠匿しただけでは、相続欠格とはなりません。
5 相続人の廃除
被相続人が死亡した場合に相続人となる者が、被相続人に対して、虐待・侮辱を行い、又は著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申立てて、その者の相続権を喪失させることができます。これを「相続人の廃除」といいます。
家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が相続権を失わせるに足る虐待・侮辱があり、もしくは著しい非行があったことを認定して初めて、排除の効力が生じます。単に親父が「おまえは勘当だ!」というだけでは廃除できません(江戸時代においても、勘当届書を奉行所に提出し、奉行所の許可が出た後に初めて効力が生じたようです。)。
相続人の廃除は、遺言で行うこともできます。
6 相続の効果
相続の効果として、相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続人が数人あるときは、相続財産は共同相続人の共有に属することになります。そして、共同相続人間の共有持分の割合は、その「相続分」(相続する割合)に応じたものになります。相続分は、被相続人が遺言で定めることができます。
遺言による相続分の指定がない場合は法が定める相続分によることになり、具体的な「法定相続分」は次の通りです。
まず、配偶者がいない場合は、子、直系尊属、兄弟姉妹などが上記2記載の順位で相続人となり、当該相続人が全部の遺産を相続します。同順位の相続人が複数いるときは、均等割りになります。
次に、配偶者がいる場合で、①子と配偶者が相続人の場合、相続分は子全員と配偶者間において、それぞれ1/2となります。②直系尊属と配偶者が相続人の場合、直系尊属全員と配偶者間において、1/3と2/3となり、③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹全員と配偶者間において、1/4と3/4になります。④配偶者だけが相続人の場合、相続分は配偶者が全部となります。
そして、上記①の子、②の直系尊属、③の兄弟姉妹が複数いるときは、その相続人間で均等割りになります。例えば、配偶者と子供が3人いる場合は、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/6(1/2×1/3=1/6)になります。
7 特別受益者制度とは
共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受け、又は婚姻や養子縁組のために贈与を受け、もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、相続人間の実質的公平を図るため、その相続分を縮小させることにしています。この制度を、「特別受益制度」といい、受益を受けた者を「特別受益者」といいます。
特別受益者の具体的な相続分の算出方法は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の割合により各共同相続人相続分を算定し、この相続分から特別受益となる遺贈又は贈与の価額を控除した残額がその特別受益者の相続分となります。この特別受益を遺産の中に回復させることを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益があるというために、贈与の場合は、婚姻のための持参金、嫁入り道具、支度金などの財産の贈与を受けるとか、生計の資本の場合は、居住用の土地・建物の購入代金、開業資金などの財産の贈与を受ける場合をいいます。学資の場合も、兄弟姉妹の中で1人だけ大学に行く学資を出してもらった場合などは、生計の資本としての贈与になると解されています。なお、遺贈については、こうした目的による限定はありません。
ただ、被相続人は、 「特別受益の持ち戻し」を免除するという意思表示をすることができます。この場合は、特別受益は渡し切りとなります。但し、これによって、共同相続人の遺留分(遺言によっても減少させることができない最低限の相続分)を侵害する場合は、遺留分減殺請求権を行使されることがあります。
8 寄与分とは
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合は、相続人間の実質的公平を図るため、寄与に相当する額の財産を寄与を行った者に取得させる「寄与分」の制度があります。
寄与分の主張ができるのは共同相続人に限られますから、内縁の妻や先に死亡した長男の妻など共同相続人でないものは、いくら被相続人の療養看護に尽力したとしても寄与分の主張はできません。
寄与の方法は、被相続人の事業である農業や家業に無給に近い状態で従事したとか、被相続人の事業の関する借金を代わって弁済した場合などが典型例です。療養看護の場合は、これによって被相続人が看護費用の支出を免れた場合などです。また、妻が夫と資金を出しあって不動産を購入したけれど不動産の名義は夫の単独名義である場合は、その他の方法による寄与ということになります。
9 遺産分割とは
上述の通り、共同相続の場合は相続財産は共同相続人の共有になりますが、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることを「遺産分割」といいます。
相続財産の分割は、通常の共有物を分割する手続きと異なり、相続財産全部を相続分と共同相続人間の実情に応じて総合的に分ける手続きです。
具体的には、相続財産に属する物や権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行われることになります。すなわち、価値としては相続分に応じたものにすることを前提に、相続財産の社会的経済的価値をできるだけ損なわず、各相続人の生計の立て方や要望を取り入れつつ、その他一切の事情を考慮しながら決めるということです。
典型例は、農業承継者に農地を分配し、事業承継者に株式を分配するなどといったことです。
なお、分割の態様には、現物を分割する現物分割、遺産を多く取得した相続人が他の相続人に対して代償金を支払って過不足を調整する代償分割、現物を換価してその代金を分配する換価分割などがあります。
また、分割は、共同相続人間の協議により決定されますが、協議が調なわないときは、家庭裁判所に審判又は調停を求めることができます。
10 相続の承認及び放棄とは
相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
しかしながら、一切の権利義務である相続財産を承継するかどうかについては、各相続人の意思にゆだねられています。すなわち、相続財産には預金、不動産、株式といった積極財産だけでなく、借金等の債務である消極財産も含まれるので、消極財産が積極財産を超えるときには相続財産を承継しないことができます。また、積極財産の方が多い場合でも承継を潔しとしないとか、他の兄弟に相続財産を譲りたいと希望するような場合も、承継しないことができます。
11 相続の承認又は放棄に関する熟慮期間とは
相続財産の承継をしない、すなわち「相続の放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
すなわち、この期間内に遺産を調査し、相続するかどうかを決めることになります。そこでは、隠れ借金の有無の調査が重要です。上述した通り、相続すれば債務も引き継ぐからです。例えば、父親が中小企業を経営しており、生前、金融機関から頻繁に融資を受け、また取引先や親族等からも借金しているような場合は注意が必要です。また、こうした場合は保証債務を負担していることも多く、こうした保証債務は、調査から漏れる可能性もあります。金融機関、取引先等にその有無を問い合わせるなどが必要です。
調査の結果、承継することになる資産よりも負債の方が多いことが判明したら、相続放棄の手続きをします。相続の放棄は、家庭裁判所に申述の手続きを行う方法によります。
なお、判然としない場合、相続財産の範囲内で債務を弁済し、もし財産が残ったらそれを相続するという「限定承認」を行うこともできます。限定承認は、放棄の手続きと同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行って手続きをします。ただ、この手続きは、放棄と異なり、複数の相続人がいる場合には、全員が共同して申し立てる必要があります。
なお、上記の3ヶ月という期間は、家庭裁判所に請求して伸長を求めることができます。
12 相続の単純承認
相続人が被相続人の権利義務の承継を無条件に受諾することを「相続の承認」といい、この場合は家庭裁判所への申述といった方式は不要です。
また、上記熟慮期間が経過すると、単純承認したとみなされます。
我々弁護士にとって、相続問題はよく相談を受ける分野であり、また多くの紛争処理の依頼を受ける分野です。
従って、ネットローでも、今後相続関連の解説記事を掲載していきたいと考えていますので、まずは、「相続の基本」について解説したいと思います。
「相続欠格」、「相続人の廃除」、「特別受益者制度」、「寄与分」、「相続の放棄」、「限定承認」などについても解説しています。
1 相続とは
相続とは、死亡などの相続原因が発生した場合に、被相続人から相続人に財産上の地位が移転する制度です。もう少し平たく言えば、私たち自然人(法人ではない人間)が死亡することによって、その自然人に帰属していたい財産や権利・義務が、子供や妻などの他の自然人によって包括的に承継される制度です。
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
2 相続人とは
被相続人の財産上の地位を承継する人のことを「相続人」といい、相続される財産や権利・義務の主体であった人を「被相続人」といいます。相続人となる人は、被相続人の子、配偶者、直系尊属及び兄弟姉妹です。胎児も、被相続人の子として相続する資格があります。
なお、内縁の妻は、内縁の夫の相続人にはなりません。内縁の妻に遺産を残すには、遺言書を書いて遺贈(遺言のよる贈与)をするか、死因贈与契約を締結しておく必要があります。
相続の順位は、被相続人の子が第1順位、(子がいない場合)被相続人の親などの直系尊属が第2順位、(子も直系尊属もいない場合)被相続人の兄弟姉妹が第3順位となります。被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記相続人と同順位になります。例えば、夫が死亡し、子と妻がいる場合は、子と妻は同順位で相続人となります。
3 代襲相続とは
相続の開始以前に被相続人の子もしくは兄弟姉妹が死亡しているけれど(したがって相続人ではない。)、仮に生存していればその者が相続人となる場合で、その者の子がいる場合には、その者の子が代わって相続します。これを「代襲相続」といいます。
また、代襲者である相続人の子が死亡している場合は、孫が代わって相続し、これを「再代襲相続」といいます。
4 相続欠格とは
次のような行為を行った者は、相続人としての資格を失います。これを「相続欠格」といいます。
① 故意に被相続人、又は相続に関し先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告訴・告発しなかった者
③ 詐欺・脅迫により、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取消をさせ、又は変更させた者
④ 詐欺・脅迫により、被相続人が③記載の行為をすることを妨げた者
⑤ 遺言書を偽造・変造し、もしくは破棄・隠匿した者
なお、遺言書ではなく、相続財産を隠匿しただけでは、相続欠格とはなりません。
5 相続人の廃除
被相続人が死亡した場合に相続人となる者が、被相続人に対して、虐待・侮辱を行い、又は著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申立てて、その者の相続権を喪失させることができます。これを「相続人の廃除」といいます。
家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が相続権を失わせるに足る虐待・侮辱があり、もしくは著しい非行があったことを認定して初めて、排除の効力が生じます。単に親父が「おまえは勘当だ!」というだけでは廃除できません(江戸時代においても、勘当届書を奉行所に提出し、奉行所の許可が出た後に初めて効力が生じたようです。)。
相続人の廃除は、遺言で行うこともできます。
6 相続の効果
相続の効果として、相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続人が数人あるときは、相続財産は共同相続人の共有に属することになります。そして、共同相続人間の共有持分の割合は、その「相続分」(相続する割合)に応じたものになります。相続分は、被相続人が遺言で定めることができます。
遺言による相続分の指定がない場合は法が定める相続分によることになり、具体的な「法定相続分」は次の通りです。
まず、配偶者がいない場合は、子、直系尊属、兄弟姉妹などが上記2記載の順位で相続人となり、当該相続人が全部の遺産を相続します。同順位の相続人が複数いるときは、均等割りになります。
次に、配偶者がいる場合で、①子と配偶者が相続人の場合、相続分は子全員と配偶者間において、それぞれ1/2となります。②直系尊属と配偶者が相続人の場合、直系尊属全員と配偶者間において、1/3と2/3となり、③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹全員と配偶者間において、1/4と3/4になります。④配偶者だけが相続人の場合、相続分は配偶者が全部となります。
そして、上記①の子、②の直系尊属、③の兄弟姉妹が複数いるときは、その相続人間で均等割りになります。例えば、配偶者と子供が3人いる場合は、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/6(1/2×1/3=1/6)になります。
7 特別受益者制度とは
共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受け、又は婚姻や養子縁組のために贈与を受け、もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、相続人間の実質的公平を図るため、その相続分を縮小させることにしています。この制度を、「特別受益制度」といい、受益を受けた者を「特別受益者」といいます。
特別受益者の具体的な相続分の算出方法は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の割合により各共同相続人相続分を算定し、この相続分から特別受益となる遺贈又は贈与の価額を控除した残額がその特別受益者の相続分となります。この特別受益を遺産の中に回復させることを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益があるというために、贈与の場合は、婚姻のための持参金、嫁入り道具、支度金などの財産の贈与を受けるとか、生計の資本の場合は、居住用の土地・建物の購入代金、開業資金などの財産の贈与を受ける場合をいいます。学資の場合も、兄弟姉妹の中で1人だけ大学に行く学資を出してもらった場合などは、生計の資本としての贈与になると解されています。なお、遺贈については、こうした目的による限定はありません。
ただ、被相続人は、 「特別受益の持ち戻し」を免除するという意思表示をすることができます。この場合は、特別受益は渡し切りとなります。但し、これによって、共同相続人の遺留分(遺言によっても減少させることができない最低限の相続分)を侵害する場合は、遺留分減殺請求権を行使されることがあります。
8 寄与分とは
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合は、相続人間の実質的公平を図るため、寄与に相当する額の財産を寄与を行った者に取得させる「寄与分」の制度があります。
寄与分の主張ができるのは共同相続人に限られますから、内縁の妻や先に死亡した長男の妻など共同相続人でないものは、いくら被相続人の療養看護に尽力したとしても寄与分の主張はできません。
寄与の方法は、被相続人の事業である農業や家業に無給に近い状態で従事したとか、被相続人の事業の関する借金を代わって弁済した場合などが典型例です。療養看護の場合は、これによって被相続人が看護費用の支出を免れた場合などです。また、妻が夫と資金を出しあって不動産を購入したけれど不動産の名義は夫の単独名義である場合は、その他の方法による寄与ということになります。
9 遺産分割とは
上述の通り、共同相続の場合は相続財産は共同相続人の共有になりますが、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることを「遺産分割」といいます。
相続財産の分割は、通常の共有物を分割する手続きと異なり、相続財産全部を相続分と共同相続人間の実情に応じて総合的に分ける手続きです。
具体的には、相続財産に属する物や権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行われることになります。すなわち、価値としては相続分に応じたものにすることを前提に、相続財産の社会的経済的価値をできるだけ損なわず、各相続人の生計の立て方や要望を取り入れつつ、その他一切の事情を考慮しながら決めるということです。
典型例は、農業承継者に農地を分配し、事業承継者に株式を分配するなどといったことです。
なお、分割の態様には、現物を分割する現物分割、遺産を多く取得した相続人が他の相続人に対して代償金を支払って過不足を調整する代償分割、現物を換価してその代金を分配する換価分割などがあります。
また、分割は、共同相続人間の協議により決定されますが、協議が調なわないときは、家庭裁判所に審判又は調停を求めることができます。
10 相続の承認及び放棄とは
相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
しかしながら、一切の権利義務である相続財産を承継するかどうかについては、各相続人の意思にゆだねられています。すなわち、相続財産には預金、不動産、株式といった積極財産だけでなく、借金等の債務である消極財産も含まれるので、消極財産が積極財産を超えるときには相続財産を承継しないことができます。また、積極財産の方が多い場合でも承継を潔しとしないとか、他の兄弟に相続財産を譲りたいと希望するような場合も、承継しないことができます。
11 相続の承認又は放棄に関する熟慮期間とは
相続財産の承継をしない、すなわち「相続の放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
すなわち、この期間内に遺産を調査し、相続するかどうかを決めることになります。そこでは、隠れ借金の有無の調査が重要です。上述した通り、相続すれば債務も引き継ぐからです。例えば、父親が中小企業を経営しており、生前、金融機関から頻繁に融資を受け、また取引先や親族等からも借金しているような場合は注意が必要です。また、こうした場合は保証債務を負担していることも多く、こうした保証債務は、調査から漏れる可能性もあります。金融機関、取引先等にその有無を問い合わせるなどが必要です。
調査の結果、承継することになる資産よりも負債の方が多いことが判明したら、相続放棄の手続きをします。相続の放棄は、家庭裁判所に申述の手続きを行う方法によります。
なお、判然としない場合、相続財産の範囲内で債務を弁済し、もし財産が残ったらそれを相続するという「限定承認」を行うこともできます。限定承認は、放棄の手続きと同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行って手続きをします。ただ、この手続きは、放棄と異なり、複数の相続人がいる場合には、全員が共同して申し立てる必要があります。
なお、上記の3ヶ月という期間は、家庭裁判所に請求して伸長を求めることができます。
12 相続の単純承認
相続人が被相続人の権利義務の承継を無条件に受諾することを「相続の承認」といい、この場合は家庭裁判所への申述といった方式は不要です。
また、上記熟慮期間が経過すると、単純承認したとみなされます。