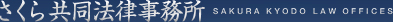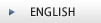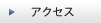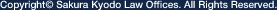■企業の所有者、ステークホルダーと言われる人たち(ブルドックソース事件)
コーポレイトガバナンスが、企業価値・株主価値の向上を実現していくために経営を監視し、経営陣を選択し、動機づけていくための仕組みであるならば、その主体は現経営陣ではありえず、それは株主であり、また資本市場であるはずである。ところが、日本企業においては、持ち合いその他の日本的経営慣行によってコーポレイトガバナンスという仕組みが十分に機能していないことが指摘されているところであり、近年、このコーポレイトガバナンスが全く機能しなかったブルドックソース事件というものがある。
この事件は、米国投資ファンドのスティール・パートナーズ(SP)が上場企業であるブルドックソース社(BS)に対し敵対的TOBをしかけ、これに対してBSが株主総会の決議を経て買収防衛策を導入・発動し、SPの買収を阻止した事件である。日本の経営慣行を顧みない憎き米国ファンドから、ソース製造業という伝統的日本企業とその伝統的経営形態をみごとに防衛した事件として肯定的に報道された事件である。
ところで、買収オファーがある時の株主に対する適切な現経営陣の受託者責任(善管注意義務)の履行方法は、買収オファー価格が会社の企業価値・株主価値よりも高額であれば株主に対して売却を勧め、オファー価格が企業価値・株主価値よりも低額であるとき、もしくは現経営陣が経営を維持することにより一定期間経過後に企業価値・株主価値がオファー価格よりも高額になるときは、株主にその根拠を説明した上で、保有を勧めることになる。すなわち、買収オファーとは、ある投資家が既存株主に対しその保有株式の買取を申し出るものであり、投資家と株主間の契約問題であって、現経営陣はその関係における当事者ではない。現経営陣が関係するとすれば、現経営陣の株主に対する受託者責任を果たすために、どちらが経済的に得か損かを判断するための情報の提供義務があるというだけである。
ところが、日本では、敵対的買収が宣告されると、会社は株主だけのものではないとか、従業員、取引先、顧客、さらには地域住民といったステークホルダー(利害関係人)全体の利益を考慮すべきであるなどという主張が現経営陣からなさることが常である。この主張は、ステークホルダーの利益を考慮しない投資家は株主になる資格がないというものであり、現経営陣が株主を選ぶという主張であって、また既存株主は、ステークホルダーの利益を考慮しない投資家には自由譲渡性が認められた株式を譲渡してはならないという驚くべき主張なのである。そして、当然のことながらステークホルダーがこうした主張を支持し、ステークホルダーの利益より企業価値・株主価値の向上を強く求める者に対しては濫用的買収者などというレッテルが貼られ、防衛策発動の根拠とされることになる。
本事件もその典型であるが、通常の敵対的買収事件よりも際だって特徴的なのは、当時の株価に相当なプレミアムを付けたオファー価格の合理性や、BSの将来企業価値・株主価値がオファー価格を超えるのか否か(オファー価格が時価より高額なのであるから通常は株主にとって売却が合理的であるはずだが、それでも売却に合理性がないと主張する理由)などについて現経営陣からは何の説明なく、ステークホルダー利益尊重論(従業員や取引先などの利益)を唱える現経営陣の主張をSP以外のほぼ全ての株主が支持し、株主総会において防衛策の導入に賛成したことである。しかも、当該防衛策は、新株予約権を発行し、SP以外の株主には普通株式を、SPには普通株式の代わりに当該株式の経済的価値相当額を現金で交付するいう防衛策として極めて不合理なものであったため(現金を交付することによってお引き取り願うというまさにグリーンメイラーにとってはうれしい防衛策)、それを発動すればBSは約21億円(アドバイザー・弁護士費用を加える28億円)の資金を流出させ、その企業価値・株主価値を大きく毀損するものであった(以後今日まで、BSの株価がオファー価格を超えたことはないし、近づいたことすらない。)。にもかかわらず、BSはSPを除くほとんど全ての株主から絶大なる支持を獲得したのである。
TOBに応じないことにより投資の効果を享受せず、さらには企業価値・株主価値を著しく毀損する防衛策に賛成する株主は、いったいどんな株主なのだろうか。メインバンクなどのような特別な関係のある者を除く一般の機関投資家は、自らの顧客である投資家に対する受託者責任(善管忠義義務)があるから、TOBに応じないことによって顧客が収受しうる利益を放棄し、さらには企業価値・株主価値を毀損し、株価の低迷をまねくことが確実に予想されるような防衛策の発動に同意するはずもないであろう。一般投資家も、同様である。そうすると、BSには、SP以外には投資を目的とした株主は存在しなかったのではないかと想像される。そうであれば、まさに持ち合いの結果であるかと思うのだが、裁判資料によるとそれほどの持ち合いはなかったようであり、持ち合いがなかったからこそ、BSは防衛策の導入を図ったようでもある。そうなると、その株主の顔が見えてこないのが、この事件の特徴なのである。結局、持ち合いとまではいかなくとも、従来からの取引先など、いわゆる投資ではなく、取引関係維持などのために株式を保有する多くの事業法人もしくは事業家などのステークホルダーが株主であり、これらの人々は株主としての利益には全く関心がない人々であったのではないかと想像されるのである。
なお、この買収防衛策の適法性については司法の場で争われたが、最高裁判所は、SPによる経営支配権の取得が企業価値・株主価値を毀損するか否かは株主が判断することであり、また、企業価値・株主価値が毀損されてもステークホルダーの利益を守ると既存株主がいうのであればその判断を尊重する、すなわち司法は、絶対多数の株主の判断には介入しないとして防衛策の導入・発動を適法とした。すなわち、「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるか否かについては、最終的には、会社の帰属主体である株主自身により判断されるべきものである。」、「BSはSPに対して多額の金員を交付することになり、それ自体、BSの企業価値を毀損し、株主の共同の利益を買いするおそれのあるものということもできないわけではないが、SP以外のほとんどの既存株主は、SPによる経営支配権の取得に伴うBSの企業価値の毀損を防ぐためには、上記金員の交付もやむをえないと判断したものといえ、この判断も尊重されるべきである。」と判示しており、司法判断としては謙抑的かつ合理的な判断であろう。
ただ、司法が謙抑的であるべき結果、上記判示内容が司法の判断としては合理的であるとしても、最終的な決定をまかされた株主の判断は全く合理性の欠けるとしかいいようがないであろう。企業価値・株主価値の最大化を図ろうとしない経営陣と、その経営陣にガバナンスをきかせないどころか、企業価値・株主価値を毀損する防衛策の導入・発動を支持する株主は、金融市場、資本市場でプレイする投資家とは異質の存在であり、コーポレイトガバナンスの基本理念から逸脱していることは明らかであろう。
なお、本件の高裁判決は、SPを濫用的買収者と認定し、金融市場、資本市場における金融取引によって利益を得ることが、何か邪悪なものであるかのような判示をしており、高裁裁判官の金融市場、資本市場に対する理解の浅薄さを露呈するというオマケがついている。
まず、「株式会社は、理念的には企業価値を可能な限り最大化してそれを株主に分配するための営利組織であるが、同時にそのような株式会社も、単独で営利追求活動ができるわけではなく、1個の社会的存在であり、対内的には従業員を抱え、対外的には取引先、消費者等との経済的な活動を通じて利益を獲得している存在であることは明らかであるから、従業員、取引先など多種多様な利害関係人(ステークホルダー)との不可分な関係を視野に入れた上で企業価値を高めていくべきものであり、企業価値について、専ら株主利益のみを考慮すれば足りるという考え方には限界があり採用することができない。」と判示し、上記ステークホルダー利益尊重論を協力に支持している。
そして、SPの属性に関し、「SPは、日本株への投資を目的とする英領ケイマン諸島法に基づいて設立された米国系投資ファンドであり、SPは、その実態は明らかではないものの、日本企業30社以上に対し、総額40億ドル以上投資してきたこと、日本企業に投資するとともに、対象企業に対し、経営陣による企業買収を持ちかけたり、株式の公開買付けを行うなどし、最終的には保有する株式を売却して高額の利益を得たことがあること、BSに対しても、多数の株式を保有した後、経営陣による企業買収を持ちかけたが拒否された後、株式を買い進め、相手方の発行済株式の全株式を取得することを目的として本件公開買付けを行うに至ったこと、本件公開買付けの開始届出書においても、あくまでも証券売買による利益を得ることを目的とし、将来相手方の株式を市場内外で売却することがあり、相手方が完全子会社化したときはその資産を処分することを見込んでいることを表明したこと、SPは、相手方からの質問に対し、日本において会社を経営したことはなく現在その予定もないこと、相手方を自ら経営するつもりがないこと、企業価値を向上させることができる提案等をどのように経営陣に提供できるか想定しているものはないこと、BSの支配権を取得した場合における事業計画や経営計画を現在のところ有していないこと等が記載されていたこと、BSの行うソース類の製造販売事業について質問の大部分については、現在のところBSの日常的な業務の経営を行うことを意図していないため回答する必要がないと考えるとの回答が記載されていたことが認められる。これらの事実に疎明資料及び審尋の全趣旨を総合すると、SPは、投資ファンドという組織の性格上、当然に顧客利益優先の受託責任を負い、成功報酬の動機付けに支えられ、それを最優先にして行動する法人であり、買収対象企業についても、対象企業の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当該会社の株式を取得後、経営陣による買収を求める一方で突然株式の公開買付けの手続に出るなど、様々な策を弄して、専ら短中期的に対象会社の株式を対象会社自身や第三者に転売することで売却益を獲得しようとし、最終的には対象会社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求しようとする存在といわざるを得ない。そして、SPは、相手方の全株式を取得するといいつつ本来協働し合うべき企業の経営面を顧慮せず、いたずらに相手方に不安を与えている。すると、このようなSPがした前記の経緯、態様による本件公開買付け等は、前記の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものとして信義誠実の原則に抵触する不当なものであり、これを行うSPは本件については濫用的買収者であると認めるのが相当というべきである。」と判示するのである。
市場関係者は、この判示内容に慄然としたことであろう。私も驚愕した。ただ、さすがに最高裁は軌道修正を行い、高裁の上記判示内容は最高裁の判断根拠には一切採用されていない。
| 本解説は、私が執筆した巻頭言「コーポレイトガバナンスとブルドックソース 事件(買収防衛策発動事件)」(季刊「社外取締役Vol.19-2009.9」、特定非営利 活動法人全国社外取締役ネットワーク、平成21年9月発行予定)に加筆した ものです。 |
コーポレイトガバナンスが、企業価値・株主価値の向上を実現していくために経営を監視し、経営陣を選択し、動機づけていくための仕組みであるならば、その主体は現経営陣ではありえず、それは株主であり、また資本市場であるはずである。ところが、日本企業においては、持ち合いその他の日本的経営慣行によってコーポレイトガバナンスという仕組みが十分に機能していないことが指摘されているところであり、近年、このコーポレイトガバナンスが全く機能しなかったブルドックソース事件というものがある。
この事件は、米国投資ファンドのスティール・パートナーズ(SP)が上場企業であるブルドックソース社(BS)に対し敵対的TOBをしかけ、これに対してBSが株主総会の決議を経て買収防衛策を導入・発動し、SPの買収を阻止した事件である。日本の経営慣行を顧みない憎き米国ファンドから、ソース製造業という伝統的日本企業とその伝統的経営形態をみごとに防衛した事件として肯定的に報道された事件である。
ところで、買収オファーがある時の株主に対する適切な現経営陣の受託者責任(善管注意義務)の履行方法は、買収オファー価格が会社の企業価値・株主価値よりも高額であれば株主に対して売却を勧め、オファー価格が企業価値・株主価値よりも低額であるとき、もしくは現経営陣が経営を維持することにより一定期間経過後に企業価値・株主価値がオファー価格よりも高額になるときは、株主にその根拠を説明した上で、保有を勧めることになる。すなわち、買収オファーとは、ある投資家が既存株主に対しその保有株式の買取を申し出るものであり、投資家と株主間の契約問題であって、現経営陣はその関係における当事者ではない。現経営陣が関係するとすれば、現経営陣の株主に対する受託者責任を果たすために、どちらが経済的に得か損かを判断するための情報の提供義務があるというだけである。
ところが、日本では、敵対的買収が宣告されると、会社は株主だけのものではないとか、従業員、取引先、顧客、さらには地域住民といったステークホルダー(利害関係人)全体の利益を考慮すべきであるなどという主張が現経営陣からなさることが常である。この主張は、ステークホルダーの利益を考慮しない投資家は株主になる資格がないというものであり、現経営陣が株主を選ぶという主張であって、また既存株主は、ステークホルダーの利益を考慮しない投資家には自由譲渡性が認められた株式を譲渡してはならないという驚くべき主張なのである。そして、当然のことながらステークホルダーがこうした主張を支持し、ステークホルダーの利益より企業価値・株主価値の向上を強く求める者に対しては濫用的買収者などというレッテルが貼られ、防衛策発動の根拠とされることになる。
本事件もその典型であるが、通常の敵対的買収事件よりも際だって特徴的なのは、当時の株価に相当なプレミアムを付けたオファー価格の合理性や、BSの将来企業価値・株主価値がオファー価格を超えるのか否か(オファー価格が時価より高額なのであるから通常は株主にとって売却が合理的であるはずだが、それでも売却に合理性がないと主張する理由)などについて現経営陣からは何の説明なく、ステークホルダー利益尊重論(従業員や取引先などの利益)を唱える現経営陣の主張をSP以外のほぼ全ての株主が支持し、株主総会において防衛策の導入に賛成したことである。しかも、当該防衛策は、新株予約権を発行し、SP以外の株主には普通株式を、SPには普通株式の代わりに当該株式の経済的価値相当額を現金で交付するいう防衛策として極めて不合理なものであったため(現金を交付することによってお引き取り願うというまさにグリーンメイラーにとってはうれしい防衛策)、それを発動すればBSは約21億円(アドバイザー・弁護士費用を加える28億円)の資金を流出させ、その企業価値・株主価値を大きく毀損するものであった(以後今日まで、BSの株価がオファー価格を超えたことはないし、近づいたことすらない。)。にもかかわらず、BSはSPを除くほとんど全ての株主から絶大なる支持を獲得したのである。
TOBに応じないことにより投資の効果を享受せず、さらには企業価値・株主価値を著しく毀損する防衛策に賛成する株主は、いったいどんな株主なのだろうか。メインバンクなどのような特別な関係のある者を除く一般の機関投資家は、自らの顧客である投資家に対する受託者責任(善管忠義義務)があるから、TOBに応じないことによって顧客が収受しうる利益を放棄し、さらには企業価値・株主価値を毀損し、株価の低迷をまねくことが確実に予想されるような防衛策の発動に同意するはずもないであろう。一般投資家も、同様である。そうすると、BSには、SP以外には投資を目的とした株主は存在しなかったのではないかと想像される。そうであれば、まさに持ち合いの結果であるかと思うのだが、裁判資料によるとそれほどの持ち合いはなかったようであり、持ち合いがなかったからこそ、BSは防衛策の導入を図ったようでもある。そうなると、その株主の顔が見えてこないのが、この事件の特徴なのである。結局、持ち合いとまではいかなくとも、従来からの取引先など、いわゆる投資ではなく、取引関係維持などのために株式を保有する多くの事業法人もしくは事業家などのステークホルダーが株主であり、これらの人々は株主としての利益には全く関心がない人々であったのではないかと想像されるのである。
なお、この買収防衛策の適法性については司法の場で争われたが、最高裁判所は、SPによる経営支配権の取得が企業価値・株主価値を毀損するか否かは株主が判断することであり、また、企業価値・株主価値が毀損されてもステークホルダーの利益を守ると既存株主がいうのであればその判断を尊重する、すなわち司法は、絶対多数の株主の判断には介入しないとして防衛策の導入・発動を適法とした。すなわち、「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるか否かについては、最終的には、会社の帰属主体である株主自身により判断されるべきものである。」、「BSはSPに対して多額の金員を交付することになり、それ自体、BSの企業価値を毀損し、株主の共同の利益を買いするおそれのあるものということもできないわけではないが、SP以外のほとんどの既存株主は、SPによる経営支配権の取得に伴うBSの企業価値の毀損を防ぐためには、上記金員の交付もやむをえないと判断したものといえ、この判断も尊重されるべきである。」と判示しており、司法判断としては謙抑的かつ合理的な判断であろう。
ただ、司法が謙抑的であるべき結果、上記判示内容が司法の判断としては合理的であるとしても、最終的な決定をまかされた株主の判断は全く合理性の欠けるとしかいいようがないであろう。企業価値・株主価値の最大化を図ろうとしない経営陣と、その経営陣にガバナンスをきかせないどころか、企業価値・株主価値を毀損する防衛策の導入・発動を支持する株主は、金融市場、資本市場でプレイする投資家とは異質の存在であり、コーポレイトガバナンスの基本理念から逸脱していることは明らかであろう。
なお、本件の高裁判決は、SPを濫用的買収者と認定し、金融市場、資本市場における金融取引によって利益を得ることが、何か邪悪なものであるかのような判示をしており、高裁裁判官の金融市場、資本市場に対する理解の浅薄さを露呈するというオマケがついている。
まず、「株式会社は、理念的には企業価値を可能な限り最大化してそれを株主に分配するための営利組織であるが、同時にそのような株式会社も、単独で営利追求活動ができるわけではなく、1個の社会的存在であり、対内的には従業員を抱え、対外的には取引先、消費者等との経済的な活動を通じて利益を獲得している存在であることは明らかであるから、従業員、取引先など多種多様な利害関係人(ステークホルダー)との不可分な関係を視野に入れた上で企業価値を高めていくべきものであり、企業価値について、専ら株主利益のみを考慮すれば足りるという考え方には限界があり採用することができない。」と判示し、上記ステークホルダー利益尊重論を協力に支持している。
そして、SPの属性に関し、「SPは、日本株への投資を目的とする英領ケイマン諸島法に基づいて設立された米国系投資ファンドであり、SPは、その実態は明らかではないものの、日本企業30社以上に対し、総額40億ドル以上投資してきたこと、日本企業に投資するとともに、対象企業に対し、経営陣による企業買収を持ちかけたり、株式の公開買付けを行うなどし、最終的には保有する株式を売却して高額の利益を得たことがあること、BSに対しても、多数の株式を保有した後、経営陣による企業買収を持ちかけたが拒否された後、株式を買い進め、相手方の発行済株式の全株式を取得することを目的として本件公開買付けを行うに至ったこと、本件公開買付けの開始届出書においても、あくまでも証券売買による利益を得ることを目的とし、将来相手方の株式を市場内外で売却することがあり、相手方が完全子会社化したときはその資産を処分することを見込んでいることを表明したこと、SPは、相手方からの質問に対し、日本において会社を経営したことはなく現在その予定もないこと、相手方を自ら経営するつもりがないこと、企業価値を向上させることができる提案等をどのように経営陣に提供できるか想定しているものはないこと、BSの支配権を取得した場合における事業計画や経営計画を現在のところ有していないこと等が記載されていたこと、BSの行うソース類の製造販売事業について質問の大部分については、現在のところBSの日常的な業務の経営を行うことを意図していないため回答する必要がないと考えるとの回答が記載されていたことが認められる。これらの事実に疎明資料及び審尋の全趣旨を総合すると、SPは、投資ファンドという組織の性格上、当然に顧客利益優先の受託責任を負い、成功報酬の動機付けに支えられ、それを最優先にして行動する法人であり、買収対象企業についても、対象企業の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当該会社の株式を取得後、経営陣による買収を求める一方で突然株式の公開買付けの手続に出るなど、様々な策を弄して、専ら短中期的に対象会社の株式を対象会社自身や第三者に転売することで売却益を獲得しようとし、最終的には対象会社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求しようとする存在といわざるを得ない。そして、SPは、相手方の全株式を取得するといいつつ本来協働し合うべき企業の経営面を顧慮せず、いたずらに相手方に不安を与えている。すると、このようなSPがした前記の経緯、態様による本件公開買付け等は、前記の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものとして信義誠実の原則に抵触する不当なものであり、これを行うSPは本件については濫用的買収者であると認めるのが相当というべきである。」と判示するのである。
市場関係者は、この判示内容に慄然としたことであろう。私も驚愕した。ただ、さすがに最高裁は軌道修正を行い、高裁の上記判示内容は最高裁の判断根拠には一切採用されていない。