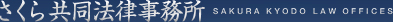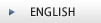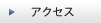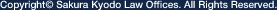1 離婚の手続きはどうなっているのですか?
一般には、両当事者が協議し、離婚することに合意した場合は、当事者が署名捺印した離婚届書(証人2名の署名捺印も必要)を市町村長に提出します。そして、これが受理されると離婚が成立することになります(民法763条、協議離婚)。
相手方が離婚に応じない場合は、まず、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。調停とは、家庭裁判所において話し合いを行い、合意による解決を図ることを目的とする手続きです。そして、調停の場でも話し合いによる解決がつかない場合は、調停不成立となり、離婚を求める当事者は訴えを提起し、訴訟に移行することになります。
2 相手が離婚はいやだといっても離婚できるのですか?
訴えを提起すれば、必ず裁判所は離婚を認めてくれるかといえば、そうでもありません。離婚が認められる場合について、民法は次の5つの離婚原因を定めています(民法770条1項)。
1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 回復の見込みのない強度の精神病
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由(継続障害事由)
昔は不貞行為(1号)を理由とするものが多かったと思われますが、近年では継続障害事由(5号)の存在を理由とするものが圧倒的に多くなっています。この離婚原因は、「継続障害事由」があることによって婚姻関係が「破綻」し、回復の見込みがないこと意味するとされています。
まず、「継続障害事由」とは、虐待、暴力などが典型とされてきましたが、近年は、相手方の怠惰な性格、勤労意欲の欠如、多額の借金などはもちろんのこと、性格の不一致、愛情の喪失、価値化の相違、思いやりのなさなども含まれ、「継続障害事由」の範囲は広範なものになっています。
また、裁判所が行う「破綻」の認定は緩やかになってきています。私の感覚では、当事者が離婚を求めて訴えを提起しているような事案では、離婚を認めるべきではない事情がない限り、基本的には「破綻」を認定するというのが裁判実務(今の裁判官の基本的発想)であろうかと思います。つまり、裁判官においても、離婚は道徳的でないとか、できたら離婚すべきでないとか、また、できるだけ婚姻関係を継続させることが望ましいなどという価値観(余計なお世話的価値観)はもっていないということです。ただ、もちろんこういう考え方は、上記民法の規定の建前とは異なりますから、裁判所がこれを正面から言うことはありませんが。
3 有責配偶者から離婚を求めることができるのですか?
このように継続障害事由が相当広範に認められ、かつ破綻の認定も緩やかになってきていますが、有責配偶者(破綻に責任がある配偶者)の方が離婚を求めるときは、裁判所は離婚を安易に認めません。
むかし、「踏んだり蹴ったり」判決という最高裁の判決があり、夫が他の女性との間に子をもうけ、妻と別居してその女性と同棲するに至ったという事案において、夫からの離婚請求を棄却するに際し、「もしかかる請求が是認されるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不道義勝手気儘を許すものではない」と判示し、有責配偶者からの離婚請求は全く認めない立場を明らかにしていました。
ただ、1987年の最高裁判決でこの考え方を若干緩め、別居期間が相当に長くなり、未成熟の子もなく、離婚により相手方が経済的な面などにおいて過酷な状態におかれるなどの社会正義に反するような事情がないときは、有責配偶者からする離婚請求も認めると判示しました。これは、夫婦ともに70歳を超え、同居期間12年に対し別居期間は35年という事案でしたので、判例変更はありましたが、裁判所は有責配偶者からする離婚請求に対しては、いまだ相当に厳しい態度で臨んでいるといえます。
ただ、たとえば性格の不一致が離婚原因として主張されるようなときに、相手方の性格を一方的に非難し、性格の不一致が生じた原因は相手方にあるから相手方が有責配偶者であるなどという主張がなされることがありますが、このような主張は一般には認められません。まあ、それはお互い様でしょうということです。
4 財産はどのように分けるのですか?
離婚をするにあたっては(離婚後でも可能)、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条)。
この財産分与の要素には次に3つがあると言われています。
【1】 夫婦の協力によって築き上げた財産の清算(清算的財産分与)
【2】 離婚後の一方当事者の生計の維持(扶養的財産分与)
【3】 相手方の有責な行為に対する精神的損害の補填(慰謝料的財産分与)
そして、具体的な分与の対象や額は、まずは当事者同士が協議することになりますが、協議が調わないときは、最終的には裁判所が、上記3要素を勘案しながら決定することになります。
5 清算的財産分与の清算割合はどうなりますか?
清算の割合については、財産形成、維持への寄与度によって決定されます。 かつては、共稼ぎ型・事業協力型と専業主婦型に分け、前者の寄与度を5割、後者のそれを3,4割とする例が見られましたが、近年は、財産形成に対する家事労働の貢献は、夫の就業による貢献と同等であるという考え方が主流であり、専業主婦の場合も清算割合は原則5割として、特段の事情がある場合には、その割合を調整することがほとんどです。そして、夫が事業を行って財産形成を行った場合も同様であるという考え方がこれまた主流であると思います。
私の経験では、よほどのことがない限り、夫婦平等(5割5割の寄与度)と裁判所は考えています。世の男性諸君!しかとご認識されたい。
6 相続した財産も分与の対象になりますか?
清算的財産分与の対象となる財産は、原則として、名義のいかんを問わず(夫の名義だろうが、妻の名義だろうが)、婚姻中に取得された財産の全てです。従って、婚姻前に取得されていた財産は除外されます。また、婚姻後に取得された財産でも、相続や親族からの贈与によって取得された財産も除外されます。
7 将来の退職金や年金は分与の対象になりますか?
将来の退職金のうち、近い将来に受領できる蓋然性の高い退職金は分与の対象となります。賃金の後払的性格のものだからです。
同じく、年金も分与の対象となります。
8 年金分割制度とはどのようなものですか?
厚生年金・共済年金は、夫婦各人の基礎年金の存在を前提としつつ、世帯単位で給付水準を決め、夫婦2人の生活が成り立つようになっています。そのため、離婚するとこの前提が崩れ、離婚後に夫と妻が受給する年金額には大きな格差が生じることになります。
この格差を埋めるために平成16年の年金制度改革により、婚姻期間中の年金分割制度が平成19年4月から、第3号被保険者期間についての年金分割制度が同20年4月から導入されました(詳しくは、社会保険庁のホームページ・離婚時の厚生年金の分割制度参照)。
9 扶養的財産分与の額はどうなりますか?
扶養的財産分与の趣旨は離婚後の一方当事者の生計を維持するためのものとはいっても、例えば離婚した妻が死亡もしくは再婚するまでの生活保障を求めるようなものではなく、生活のための収入を得るための準備期間中の一時的な扶養という趣旨です。専業主婦であった妻でも離婚後は、自己責任のもとに自活していかなければなりません。
従って、この財産分与は、清算的財産分与がなされても、なお相手に扶養の必要性がある場合に考慮される補充的なものということになります。
10 慰謝料的財産分与とは別に、有責配偶者に対して慰謝料を請求することができますか?
判例上、慰謝料は、財産分与の額や方法を決めるときにその要素として考慮されることがありますが、ここでは考慮しないで、別途単独に慰謝料を算定し、金銭で支払われることもあります。
従って、財産分与の額を決定する時に、慰謝料を含める趣旨か否かを明らかにしておく必要があります。
なお、その額は、東京地方裁判所の統計で、400万円から1000万円が20%、400万円以下が80%というものがあります。
11 財産分与に関する課税関係はどうなりますか?
【1】 金銭給付の場合
給付が金銭によって行われる場合は、原則として、給付受領者に対する課税はありません。相続税基本通達9−8は、贈与税の対象とならないことを規定しています。財産分与の本質が、夫婦が協力して築き上げた財産の清算だからです。同じ理由で、所得税も課税されません。
なお、金銭による分与者にも課税はありません。
慰謝料は、損害賠償金ですから、非課税所得とされています(所税9条1項16号、所税令30条1項)。給付者も受領者も、課税されません。
例外として、分与の額が過当であり、贈与税もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合には贈与となります(上記通達但書き)。
【2】 不動産等の場合
分与が不動産などで行われる場合は、分与者には譲渡所得税が課せられます(所得税基本通達33−1の4)。すなわち、不動産が値上がりしており、分与時の時価から取得費及び譲渡費用を控除した場合に譲渡益が発生すれば、この譲渡益に対し給付者に課税されます。ただ、分与者の居住用の土地建物を分与する場合は、特別控除の適用の余地があります(前特措35条1項)。
一般には、両当事者が協議し、離婚することに合意した場合は、当事者が署名捺印した離婚届書(証人2名の署名捺印も必要)を市町村長に提出します。そして、これが受理されると離婚が成立することになります(民法763条、協議離婚)。
相手方が離婚に応じない場合は、まず、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。調停とは、家庭裁判所において話し合いを行い、合意による解決を図ることを目的とする手続きです。そして、調停の場でも話し合いによる解決がつかない場合は、調停不成立となり、離婚を求める当事者は訴えを提起し、訴訟に移行することになります。
2 相手が離婚はいやだといっても離婚できるのですか?
訴えを提起すれば、必ず裁判所は離婚を認めてくれるかといえば、そうでもありません。離婚が認められる場合について、民法は次の5つの離婚原因を定めています(民法770条1項)。
1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 回復の見込みのない強度の精神病
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由(継続障害事由)
昔は不貞行為(1号)を理由とするものが多かったと思われますが、近年では継続障害事由(5号)の存在を理由とするものが圧倒的に多くなっています。この離婚原因は、「継続障害事由」があることによって婚姻関係が「破綻」し、回復の見込みがないこと意味するとされています。
まず、「継続障害事由」とは、虐待、暴力などが典型とされてきましたが、近年は、相手方の怠惰な性格、勤労意欲の欠如、多額の借金などはもちろんのこと、性格の不一致、愛情の喪失、価値化の相違、思いやりのなさなども含まれ、「継続障害事由」の範囲は広範なものになっています。
また、裁判所が行う「破綻」の認定は緩やかになってきています。私の感覚では、当事者が離婚を求めて訴えを提起しているような事案では、離婚を認めるべきではない事情がない限り、基本的には「破綻」を認定するというのが裁判実務(今の裁判官の基本的発想)であろうかと思います。つまり、裁判官においても、離婚は道徳的でないとか、できたら離婚すべきでないとか、また、できるだけ婚姻関係を継続させることが望ましいなどという価値観(余計なお世話的価値観)はもっていないということです。ただ、もちろんこういう考え方は、上記民法の規定の建前とは異なりますから、裁判所がこれを正面から言うことはありませんが。
3 有責配偶者から離婚を求めることができるのですか?
このように継続障害事由が相当広範に認められ、かつ破綻の認定も緩やかになってきていますが、有責配偶者(破綻に責任がある配偶者)の方が離婚を求めるときは、裁判所は離婚を安易に認めません。
むかし、「踏んだり蹴ったり」判決という最高裁の判決があり、夫が他の女性との間に子をもうけ、妻と別居してその女性と同棲するに至ったという事案において、夫からの離婚請求を棄却するに際し、「もしかかる請求が是認されるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくの如き不道義勝手気儘を許すものではない」と判示し、有責配偶者からの離婚請求は全く認めない立場を明らかにしていました。
ただ、1987年の最高裁判決でこの考え方を若干緩め、別居期間が相当に長くなり、未成熟の子もなく、離婚により相手方が経済的な面などにおいて過酷な状態におかれるなどの社会正義に反するような事情がないときは、有責配偶者からする離婚請求も認めると判示しました。これは、夫婦ともに70歳を超え、同居期間12年に対し別居期間は35年という事案でしたので、判例変更はありましたが、裁判所は有責配偶者からする離婚請求に対しては、いまだ相当に厳しい態度で臨んでいるといえます。
ただ、たとえば性格の不一致が離婚原因として主張されるようなときに、相手方の性格を一方的に非難し、性格の不一致が生じた原因は相手方にあるから相手方が有責配偶者であるなどという主張がなされることがありますが、このような主張は一般には認められません。まあ、それはお互い様でしょうということです。
4 財産はどのように分けるのですか?
離婚をするにあたっては(離婚後でも可能)、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条)。
この財産分与の要素には次に3つがあると言われています。
【1】 夫婦の協力によって築き上げた財産の清算(清算的財産分与)
【2】 離婚後の一方当事者の生計の維持(扶養的財産分与)
【3】 相手方の有責な行為に対する精神的損害の補填(慰謝料的財産分与)
そして、具体的な分与の対象や額は、まずは当事者同士が協議することになりますが、協議が調わないときは、最終的には裁判所が、上記3要素を勘案しながら決定することになります。
5 清算的財産分与の清算割合はどうなりますか?
清算の割合については、財産形成、維持への寄与度によって決定されます。 かつては、共稼ぎ型・事業協力型と専業主婦型に分け、前者の寄与度を5割、後者のそれを3,4割とする例が見られましたが、近年は、財産形成に対する家事労働の貢献は、夫の就業による貢献と同等であるという考え方が主流であり、専業主婦の場合も清算割合は原則5割として、特段の事情がある場合には、その割合を調整することがほとんどです。そして、夫が事業を行って財産形成を行った場合も同様であるという考え方がこれまた主流であると思います。
私の経験では、よほどのことがない限り、夫婦平等(5割5割の寄与度)と裁判所は考えています。世の男性諸君!しかとご認識されたい。
6 相続した財産も分与の対象になりますか?
清算的財産分与の対象となる財産は、原則として、名義のいかんを問わず(夫の名義だろうが、妻の名義だろうが)、婚姻中に取得された財産の全てです。従って、婚姻前に取得されていた財産は除外されます。また、婚姻後に取得された財産でも、相続や親族からの贈与によって取得された財産も除外されます。
7 将来の退職金や年金は分与の対象になりますか?
将来の退職金のうち、近い将来に受領できる蓋然性の高い退職金は分与の対象となります。賃金の後払的性格のものだからです。
同じく、年金も分与の対象となります。
8 年金分割制度とはどのようなものですか?
厚生年金・共済年金は、夫婦各人の基礎年金の存在を前提としつつ、世帯単位で給付水準を決め、夫婦2人の生活が成り立つようになっています。そのため、離婚するとこの前提が崩れ、離婚後に夫と妻が受給する年金額には大きな格差が生じることになります。
この格差を埋めるために平成16年の年金制度改革により、婚姻期間中の年金分割制度が平成19年4月から、第3号被保険者期間についての年金分割制度が同20年4月から導入されました(詳しくは、社会保険庁のホームページ・離婚時の厚生年金の分割制度参照)。
9 扶養的財産分与の額はどうなりますか?
扶養的財産分与の趣旨は離婚後の一方当事者の生計を維持するためのものとはいっても、例えば離婚した妻が死亡もしくは再婚するまでの生活保障を求めるようなものではなく、生活のための収入を得るための準備期間中の一時的な扶養という趣旨です。専業主婦であった妻でも離婚後は、自己責任のもとに自活していかなければなりません。
従って、この財産分与は、清算的財産分与がなされても、なお相手に扶養の必要性がある場合に考慮される補充的なものということになります。
10 慰謝料的財産分与とは別に、有責配偶者に対して慰謝料を請求することができますか?
判例上、慰謝料は、財産分与の額や方法を決めるときにその要素として考慮されることがありますが、ここでは考慮しないで、別途単独に慰謝料を算定し、金銭で支払われることもあります。
従って、財産分与の額を決定する時に、慰謝料を含める趣旨か否かを明らかにしておく必要があります。
なお、その額は、東京地方裁判所の統計で、400万円から1000万円が20%、400万円以下が80%というものがあります。
11 財産分与に関する課税関係はどうなりますか?
【1】 金銭給付の場合
給付が金銭によって行われる場合は、原則として、給付受領者に対する課税はありません。相続税基本通達9−8は、贈与税の対象とならないことを規定しています。財産分与の本質が、夫婦が協力して築き上げた財産の清算だからです。同じ理由で、所得税も課税されません。
なお、金銭による分与者にも課税はありません。
慰謝料は、損害賠償金ですから、非課税所得とされています(所税9条1項16号、所税令30条1項)。給付者も受領者も、課税されません。
例外として、分与の額が過当であり、贈与税もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合には贈与となります(上記通達但書き)。
【2】 不動産等の場合
分与が不動産などで行われる場合は、分与者には譲渡所得税が課せられます(所得税基本通達33−1の4)。すなわち、不動産が値上がりしており、分与時の時価から取得費及び譲渡費用を控除した場合に譲渡益が発生すれば、この譲渡益に対し給付者に課税されます。ただ、分与者の居住用の土地建物を分与する場合は、特別控除の適用の余地があります(前特措35条1項)。