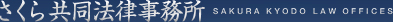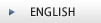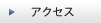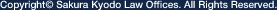2「内部通報後の社内調査の方法」〜社内調査の具体的な進め方〜
 さくら共同法律事務所 弁護士 荒竹純一氏
さくら共同法律事務所 弁護士 荒竹純一氏
Ⅰ 社内調査の特徴と調査協力義務
特捜部の捜査もまずは任意捜査
通報があった時には通報内容が真実かどうかの真相を解明していくことになりますが、なかなか思うように社内調査が進まないと感じられることが多いのはないでしょうか。そして、社内調査には警察や検察のような強制力がないのだから、調査対象者が調査に応じなければ、それ以上調査のやりようがないと思われているかもしれません。
しかしながら、権力による捜査も基本は任意捜査です。例えば、東京地検の特捜部でも参考人や被疑者から任意に事情を聞いて供述証書をつくり、証拠物に関しても任意の提出を求めるという作業が基本になります。そして、ある程度の真相の解明ができ、もう立件できるというところで、最後の証拠固めのために強制捜査をするという手法が通常取られています。
また、皆さんが行う調査の対象者はまず社員になると思いますが、この場合の調査には一定の強制力があります。
調査対象者から供述を得るとき
社内調査は、まず調査対象者である社員、もしくは参考人としての社員から話を聞くことから始まりますが、社員と会社の間には、法的に言うと雇用契約に基づく権利と義務の関係があります。そして、この雇用契約や就業規則、社内規定などが根拠になって、社員は会社の業務上必要な範囲において「調査に協力する義務がある」ことになります。
対象となる社員が調査に任意に応じないときは、「何月何日にどこに行って、調査担当者である誰々の調査を受けるように」とか、「知っている事実関係について書面にして誰々に提出してください」などと業務命令を出すことができるわけです。社員はこれに対して従う義務があります。そういう意味での強制力はあります。
こうした会社の調査権に対しては、調査対象者からプライバシーなどを理由として、調査は許されないという反論がなされることがあり、裁判で争われたケースもあります。
私的メールに関する判例
たとえば、会社のパソコンを使用した私的メールに対し、会社の調査権が及ぶかということが問題となった裁判例があります。
まず、前提として、社員が会社のパソコン使用して私的メールを送信することが許されるのかという問題があります。これについて判例は、メールの送信が職務遂行の妨げにならない態様で行われる場合には、外部からの連絡に適宜即応するために必要であるし、会社の経済的負担も極めて軽微なものであるから、私用電話と同じようなものであって、私的メールの送信も許されるという考え方を示しています。
そうすると、社員としては「使用が許され、かつ私的メールなのだからプライバシーがある」はずであり、したがって会社がその内容等について調査をすることは、プライバシーの侵害だという主張をしたいところです。
ただ、この判例は、メールの送受信の内容について社内調査の必要が生じた場合、合理的な範囲で会社は調査可能であるとしています。この事案はセクハラの事例でした。ある女性社員が「上司から食事に誘われたとか、忘年会の席上で抱きつかれた、これはセクハラだ」という内容のメールを誤ってその上司に送ってしまったため、この上司がサーバの管理部門に依頼して彼女の私的メールを自分のパソコンに転送させて監視していたという事案です。この判例は、上司が自分の部下の行動を監視することに全く合理性がないわけではないということで、プライバシーの侵害ということはできないと判示しました。
このようなケースの場合、当該上司ではなく、調査委員会もしくは調査担当者が調査するのでしたら、プライバシーの侵害があるということはできないでしょうが、嫌疑をかけられている上司が監視をしたという点において問題がなくもありません。
同じような事案において、先の判例よりも調査の許される範囲を緩やかに認めるものもあります。この判例は、私的メールのデータというものは、会社が所有して管理するファイルサーバの中にあるので、プライバシーはもともとないという考えかたを示しています。
いずれにしても、会社としては、メールは常にモニタリングすることを事前に告知しておくとよいと思います。
私的所有物、プライベートな書類などの提出義務
社内調査では、社員が所持している会社の所有物や書類の提出も、社員が任意の提出を拒む場合、業務命令という形でそれを命じることができます。
次に、私有物であるパソコンに保存された業務に関する電子メールや情報にも会社の調査権が及ぶと解されます。「業務に関する電子メールだから、その内容を明らかにせよ」ということができるということです。具体的には、該当部分をプリントアウトするようにとか、該当部分を閲覧させるように要請することになります。私的な手帳の中の業務に関する記述の部分のコピーを求めることもできるでしょう。ただ、この場合、拒絶されても強制する方法はありません。業務命令に反したとして、社員を処分し、場合によっては懲戒解雇することができる場合もあるかもしれませんが、私有物であるパソコンに保存された内容を強制的に閲覧するなどといった強制力はありません。
また、社員に私有物の提出義務はありませんが、任意で提出してもらうことに問題はありません。したがって、私有物だからといって諦めず、本人にも参考人にも任意に提出するよう説得することは問題ありませんから、努力していただきたいと思います。
こうした点は、警察や検察などの強制捜査とは異なる限界ではあります。
■真相解明はどこまでするのか?
いちばん緻密な調査を要求されるのは警察や検察に対する告訴・告発を目的としたときです。横領事件などを含め社内で発生した事件の場合は警察などは自ら積極的に動かないことがあります。このような場合は、社内で時間と労力と費用を投下して証拠を集め、嫌疑をきちんと固めてから告訴・告発をする必要があります。
調査対象となった事実を理由に社員を懲戒解雇する場合は、その後、訴訟で懲戒解雇されるような理由がないとして争われる可能性がありますので、この場合も相当に緻密な調査をしておく必要があります。
譴責処分などの場合で社員本人の納得があるような場合は、証拠固めの程度は低くなるでしょう。本人が始末書を出して終わらせるような場合も同様です。
Ⅱ社内調査の具体的な進め方
通報者から事情を聴き取り、証拠を集める
内部通報があり、調査が必要だと判断される場合に社内調査を開始します。
まず、通報者が匿名ではなく、調査に応じてくれる場合は、通報動機を見極めることも重要です。通報者の供述を聴きながらその通報動機を探り、その信用性を吟味します。
そこでは、通報者といえども自分の都合の悪いことは隠しておくのは人間の常ですから、通報者の通報内容が全てが正しいと決めつけてはいけません。
そして、通報者の通報内容の裏付けになるような客観的資料の提出もお願いする必要があります。
第三者から供述を取る場合
社内の第三者に対し「内部通報がありました。あなたの周りでの出来事のようなので、知っている内容について聞かせてもらえませんか」という依頼を行うと、調査に協力的な人、消極的な人、中立的な人などが出てきます。
協力的な人、たとえば「まさにそのとおりです。私も見ました」などと即座に供述する人については、なぜこの人は協力的なのかという動機を見極める必要があります。派閥抗争中の相手方から出てくる供述や情報は信用性が欠ける場合があります。また、女性へのセクハラに対して、「あれはセクハラではない。本人も喜んでいましたよ」などと否定的な見解を述べる同僚を安易に信用してはいけません。嫉妬や好き嫌いなどの感情が関係している場合もあり、注意が必要です。
協力的でない人についても、その理由を見極める必要があります。自分も調査対象事実に関係しているからなのか、単に関わり合いになりたくないからなのかなどを判断します。後者であれば、事案の解明が会社にとっても重要なことを伝えて説得すれば、中立的で、信用性のある供述を得られることがあります。
中立的な人は、人の悪口は言いたくないなどというのが理由の場合があります。このような場合も、事案解明の重要性を伝えて説得することが重要となります。
共犯的立場の人から供述を取る場合
共犯的立場の人、共犯とまではいかないものの何らかの関与をしている人などに対してどう対応するかは非常に悩ましい問題です。供述の取り方は、これまで述べてきたノウハウと基本的には一緒ですが、いわゆる「利益誘導の可否」が問題となります。
「あなたは関与が低いから、正直にしゃべってくれれば、あなたは罰しませんよ」というような利益誘導をしてもいいのかどうかです。ある程度、事案の全体像が見えてきたところで、「社内処分についてはこの程度に止めておくから、きちんと話してください」というやり方は許されるでしょうし、合理的な一つの方法です。しかしこの場合、社内で利益誘導の可否に関しきちんと協議し、権限がある人の決済を得た上で、調査担当者が駆け引きに使うことになります。
ただ、刑事事件になるような事案については、共犯者的な人を罰するかどうかは司法当局の判断になりますので、注意が必要です。
調査対象者から供述をとる場合
真実を話してもらうためには、周到な事前準備が必須です。
(1)調査対象者の供述の信頼性を確認するために、それまでに収集した事実関係を時系列にして整理しておくことが大切です。証拠物の内容、第三者の供述内容についても頭に入れておきます。
(2)1人では限界がありますので、複数名で役割を決めて聴く体制を取ります。
(3)誘導尋問をしないことが肝要です。調査対象者に自ら供述をしてもらって初めてその信用性に関する判断ができます。また、まだこちらが把握していない事実まで供述が得られることがあります。万が一嘘の弁解だと思っても徹底的に聞きます。嘘の弁解が出れば出るほど、第三者の供述や証拠物と合わない部分が出てきますので、信用性がないことについて確信がもてます。このような場合、できればこの段階で、嘘の弁解を内容とする供述録取書を一回作ります。
反対尋問をするときのポイント
次の段階では、本人に第三者の供述との矛盾点や証拠物を突きながら、真実を供述してもらうようにします。大事なのは、「こういう事実があれば、こうするのは当たり前」というような推認部分で議論をしないことです。また「こんな証拠があるのだから、こうとした考えられない」などと証拠の評価でも議論をしないことが大切です。
●録音の適否
調査対象者が録音機器などを持ち込み、録音を要望することがありますが、会社の管理権の問題として拒否することは可能です。
反対に調査担当者が録音すると、言った、言わないという議論は回避できますが、録音することを明らかにした上で供述を取ろうとすると、調査対象者が過度に慎重になり、スムーズな供述がなされないことがあります。
そのデメリット回避のために、録音することを伝えずに録音する方法があります。民事訴訟の場合、原則として証拠能力に制限はありませんので、黙って録音したものも証拠として使えないことはありません。
●証拠化の方法
供述録取書(供述を記録したもの)には、本人の署名捺印が必要です。ワープロ打ちした書類に、捺印するだけは駄目です。供述内容を全て自書するのがいちばんですが、それができない場合には、会社側で供述内容をまとめた書面に自署してもらいます。
後の裁判の際に、怒鳴られた、監禁された、4〜5人に囲まれて詰問口調で自白を迫られたなどという主張をされて供述内容の信用性を争われないように、いつでも出入りが自由な場所で尋問を行って、調書を作成することが重要です。
●物的証拠の確保
本人が保管している会社の所有物を証拠とするために、本人の不在時に机の引出等から確保することも合理的な範囲では許されるでしょう。本人が保管している会社の書類等を秘密裏に閲覧することも同様でしょう。メールについて閲覧が可能であることはすでに説明しました。
しかしながら、私物については、これを本人の承諾なく確保することはできません。ただ、本人の承諾のもと任意の提出を得ることはできます。任意の提出を得て私物を預かる場合、後に会社が勝手に持って行ったなどと言われないように、「今回の件、○○を任意に提出し、会社に対してお預けいたします」という内容の同意書(自書であることが好ましい。少なくとも自署があること)を取っておくべきです。
●パソコンデータの解析
メールの内容は真相解明に非常に役立ちます。ライブドアの堀江氏の事件の場合、東京地検特捜部は、本人たちの供述を取る前にまず家宅捜索に入り、電子メールを確保してその内容が消去されることを回避することを優先する捜査手法を取りました。本人もしくはその関係者から供述を取ることよりも、客観的に証拠となる電子メールの確保を最優先にして強制捜査を行ったのです。
メールの重要性は、社内調査の場合も同様です。この場合、調査対象者によりメールが消去されていることが多々ありますが、解析専門の会社に依頼すればその復元が可能な場合があります。多少の費用がかかってもできるだけ消去データの復元をすることが真相の解明につながることになります。
Ⅲ5つの事例を紹介します
ケース1 セクハラ事件
同僚女性社員の多くが「セクハラはない」という供述を行い、会社が同僚女性社員の供述だからということでこれを全面的に信用してしまったところ、裁判ではこれら女性社員の供述が真実ではないことが判明し、会社が敗訴してしまったという事件です。女性同僚がもっていた被害者に対する妬みの感情が真実ではない供述をした理由のようです。
ケース2 セクハラ事件
1とは逆に、女性社員のセクハラの申し立てを、客観的裏付けもないまま女性の担当役員がそのまま信用してしまった事件です。女性は男性に気にくわないことをされたので、その腹いせに些細なことを大げさに取り上げてセクハラがあったなどという申し立てをしたのですが、女性役員はこうした調査になれていなかった(初めて扱った)のと女性同士ということで安易に同情し、セクハラがあった信用してしまったという事案です。
裁判では、会社側敗訴となりました。
ケース3 セクハラ事件
セクハラがあったと女性社員が男性役員に個人的に相談したものの真剣に対応してくれないとして、監督官庁に不平の申し立てをしました。
この会社は、監督官庁から管理体制ができていないとして注意をうけることになりましたが、セクハラホットラインや、内部通報制度の確立の重要性を認識することになった事件でした。
ケース4 セクハラ事件
セクハラがあったと女性社員からの申し立てがあり、調査の結果女性の言っていることが真実であるという判断に傾きつつあったものの、解析会社に依頼して消去されたメールを復元してもらったところ、その女性の言い分とは違うメールがたくさん出てきたという事案です。
ケース5 横領事件
社員が会社の商品を横流しし、その売却代金を得ていたという事件です。
まず、若い社員が高級車を乗り回しているという内部通報が寄せられました。担当者が事情を聴いたところ、本人は観念し、横領の事実を自白しました。そして、裏付け資料を確保するために、携帯電話や売却代金が振り込まれている預金通帳を任意で提出してもらい、任意で提出した旨の同意書も取って証拠物を確保した上で、刑事告訴を行ったという事件でした。
ケース6 背任事件
このケースは会社の取締役の背任行為が対象になった事件です。
異変に気づいた役員が顧問弁護士に相談し、弁護士マターとして調査が開始されました。ある程度の客観的証拠が揃った段階で、まず直属の部下である部長に対して事情を聴くことにしたところ、1回目の事情聴取には出てきてある程度の供述をしましたが、その後は聴取を拒否するのでこれに応じるよう業務命令を出しましたが、従いませんでした。その後辞表が提出され出社しなくなりました。そのため、当該部長からはほとんど話が聞けなかったという事案です。
やむをえず、その他の社員などから話を聞くなどして間接事実を積み上げ(直接の関与者は当該部長以外にいなかった)、訴訟を提起することができました。業務命令を出すことによって聴取に応じる義務を課すことはできるが、これに応じなくても強制力がないという事案です。
 さくら共同法律事務所 弁護士 荒竹純一氏
さくら共同法律事務所 弁護士 荒竹純一氏Ⅰ 社内調査の特徴と調査協力義務
特捜部の捜査もまずは任意捜査
通報があった時には通報内容が真実かどうかの真相を解明していくことになりますが、なかなか思うように社内調査が進まないと感じられることが多いのはないでしょうか。そして、社内調査には警察や検察のような強制力がないのだから、調査対象者が調査に応じなければ、それ以上調査のやりようがないと思われているかもしれません。
しかしながら、権力による捜査も基本は任意捜査です。例えば、東京地検の特捜部でも参考人や被疑者から任意に事情を聞いて供述証書をつくり、証拠物に関しても任意の提出を求めるという作業が基本になります。そして、ある程度の真相の解明ができ、もう立件できるというところで、最後の証拠固めのために強制捜査をするという手法が通常取られています。
また、皆さんが行う調査の対象者はまず社員になると思いますが、この場合の調査には一定の強制力があります。
調査対象者から供述を得るとき
社内調査は、まず調査対象者である社員、もしくは参考人としての社員から話を聞くことから始まりますが、社員と会社の間には、法的に言うと雇用契約に基づく権利と義務の関係があります。そして、この雇用契約や就業規則、社内規定などが根拠になって、社員は会社の業務上必要な範囲において「調査に協力する義務がある」ことになります。
対象となる社員が調査に任意に応じないときは、「何月何日にどこに行って、調査担当者である誰々の調査を受けるように」とか、「知っている事実関係について書面にして誰々に提出してください」などと業務命令を出すことができるわけです。社員はこれに対して従う義務があります。そういう意味での強制力はあります。
こうした会社の調査権に対しては、調査対象者からプライバシーなどを理由として、調査は許されないという反論がなされることがあり、裁判で争われたケースもあります。
私的メールに関する判例
たとえば、会社のパソコンを使用した私的メールに対し、会社の調査権が及ぶかということが問題となった裁判例があります。
まず、前提として、社員が会社のパソコン使用して私的メールを送信することが許されるのかという問題があります。これについて判例は、メールの送信が職務遂行の妨げにならない態様で行われる場合には、外部からの連絡に適宜即応するために必要であるし、会社の経済的負担も極めて軽微なものであるから、私用電話と同じようなものであって、私的メールの送信も許されるという考え方を示しています。
そうすると、社員としては「使用が許され、かつ私的メールなのだからプライバシーがある」はずであり、したがって会社がその内容等について調査をすることは、プライバシーの侵害だという主張をしたいところです。
ただ、この判例は、メールの送受信の内容について社内調査の必要が生じた場合、合理的な範囲で会社は調査可能であるとしています。この事案はセクハラの事例でした。ある女性社員が「上司から食事に誘われたとか、忘年会の席上で抱きつかれた、これはセクハラだ」という内容のメールを誤ってその上司に送ってしまったため、この上司がサーバの管理部門に依頼して彼女の私的メールを自分のパソコンに転送させて監視していたという事案です。この判例は、上司が自分の部下の行動を監視することに全く合理性がないわけではないということで、プライバシーの侵害ということはできないと判示しました。
このようなケースの場合、当該上司ではなく、調査委員会もしくは調査担当者が調査するのでしたら、プライバシーの侵害があるということはできないでしょうが、嫌疑をかけられている上司が監視をしたという点において問題がなくもありません。
同じような事案において、先の判例よりも調査の許される範囲を緩やかに認めるものもあります。この判例は、私的メールのデータというものは、会社が所有して管理するファイルサーバの中にあるので、プライバシーはもともとないという考えかたを示しています。
いずれにしても、会社としては、メールは常にモニタリングすることを事前に告知しておくとよいと思います。
私的所有物、プライベートな書類などの提出義務
社内調査では、社員が所持している会社の所有物や書類の提出も、社員が任意の提出を拒む場合、業務命令という形でそれを命じることができます。
次に、私有物であるパソコンに保存された業務に関する電子メールや情報にも会社の調査権が及ぶと解されます。「業務に関する電子メールだから、その内容を明らかにせよ」ということができるということです。具体的には、該当部分をプリントアウトするようにとか、該当部分を閲覧させるように要請することになります。私的な手帳の中の業務に関する記述の部分のコピーを求めることもできるでしょう。ただ、この場合、拒絶されても強制する方法はありません。業務命令に反したとして、社員を処分し、場合によっては懲戒解雇することができる場合もあるかもしれませんが、私有物であるパソコンに保存された内容を強制的に閲覧するなどといった強制力はありません。
また、社員に私有物の提出義務はありませんが、任意で提出してもらうことに問題はありません。したがって、私有物だからといって諦めず、本人にも参考人にも任意に提出するよう説得することは問題ありませんから、努力していただきたいと思います。
こうした点は、警察や検察などの強制捜査とは異なる限界ではあります。
■真相解明はどこまでするのか?
いちばん緻密な調査を要求されるのは警察や検察に対する告訴・告発を目的としたときです。横領事件などを含め社内で発生した事件の場合は警察などは自ら積極的に動かないことがあります。このような場合は、社内で時間と労力と費用を投下して証拠を集め、嫌疑をきちんと固めてから告訴・告発をする必要があります。
調査対象となった事実を理由に社員を懲戒解雇する場合は、その後、訴訟で懲戒解雇されるような理由がないとして争われる可能性がありますので、この場合も相当に緻密な調査をしておく必要があります。
譴責処分などの場合で社員本人の納得があるような場合は、証拠固めの程度は低くなるでしょう。本人が始末書を出して終わらせるような場合も同様です。
Ⅱ社内調査の具体的な進め方
通報者から事情を聴き取り、証拠を集める
内部通報があり、調査が必要だと判断される場合に社内調査を開始します。
まず、通報者が匿名ではなく、調査に応じてくれる場合は、通報動機を見極めることも重要です。通報者の供述を聴きながらその通報動機を探り、その信用性を吟味します。
そこでは、通報者といえども自分の都合の悪いことは隠しておくのは人間の常ですから、通報者の通報内容が全てが正しいと決めつけてはいけません。
そして、通報者の通報内容の裏付けになるような客観的資料の提出もお願いする必要があります。
第三者から供述を取る場合
社内の第三者に対し「内部通報がありました。あなたの周りでの出来事のようなので、知っている内容について聞かせてもらえませんか」という依頼を行うと、調査に協力的な人、消極的な人、中立的な人などが出てきます。
協力的な人、たとえば「まさにそのとおりです。私も見ました」などと即座に供述する人については、なぜこの人は協力的なのかという動機を見極める必要があります。派閥抗争中の相手方から出てくる供述や情報は信用性が欠ける場合があります。また、女性へのセクハラに対して、「あれはセクハラではない。本人も喜んでいましたよ」などと否定的な見解を述べる同僚を安易に信用してはいけません。嫉妬や好き嫌いなどの感情が関係している場合もあり、注意が必要です。
協力的でない人についても、その理由を見極める必要があります。自分も調査対象事実に関係しているからなのか、単に関わり合いになりたくないからなのかなどを判断します。後者であれば、事案の解明が会社にとっても重要なことを伝えて説得すれば、中立的で、信用性のある供述を得られることがあります。
中立的な人は、人の悪口は言いたくないなどというのが理由の場合があります。このような場合も、事案解明の重要性を伝えて説得することが重要となります。
共犯的立場の人から供述を取る場合
共犯的立場の人、共犯とまではいかないものの何らかの関与をしている人などに対してどう対応するかは非常に悩ましい問題です。供述の取り方は、これまで述べてきたノウハウと基本的には一緒ですが、いわゆる「利益誘導の可否」が問題となります。
「あなたは関与が低いから、正直にしゃべってくれれば、あなたは罰しませんよ」というような利益誘導をしてもいいのかどうかです。ある程度、事案の全体像が見えてきたところで、「社内処分についてはこの程度に止めておくから、きちんと話してください」というやり方は許されるでしょうし、合理的な一つの方法です。しかしこの場合、社内で利益誘導の可否に関しきちんと協議し、権限がある人の決済を得た上で、調査担当者が駆け引きに使うことになります。
ただ、刑事事件になるような事案については、共犯者的な人を罰するかどうかは司法当局の判断になりますので、注意が必要です。
調査対象者から供述をとる場合
真実を話してもらうためには、周到な事前準備が必須です。
(1)調査対象者の供述の信頼性を確認するために、それまでに収集した事実関係を時系列にして整理しておくことが大切です。証拠物の内容、第三者の供述内容についても頭に入れておきます。
(2)1人では限界がありますので、複数名で役割を決めて聴く体制を取ります。
(3)誘導尋問をしないことが肝要です。調査対象者に自ら供述をしてもらって初めてその信用性に関する判断ができます。また、まだこちらが把握していない事実まで供述が得られることがあります。万が一嘘の弁解だと思っても徹底的に聞きます。嘘の弁解が出れば出るほど、第三者の供述や証拠物と合わない部分が出てきますので、信用性がないことについて確信がもてます。このような場合、できればこの段階で、嘘の弁解を内容とする供述録取書を一回作ります。
反対尋問をするときのポイント
次の段階では、本人に第三者の供述との矛盾点や証拠物を突きながら、真実を供述してもらうようにします。大事なのは、「こういう事実があれば、こうするのは当たり前」というような推認部分で議論をしないことです。また「こんな証拠があるのだから、こうとした考えられない」などと証拠の評価でも議論をしないことが大切です。
●録音の適否
調査対象者が録音機器などを持ち込み、録音を要望することがありますが、会社の管理権の問題として拒否することは可能です。
反対に調査担当者が録音すると、言った、言わないという議論は回避できますが、録音することを明らかにした上で供述を取ろうとすると、調査対象者が過度に慎重になり、スムーズな供述がなされないことがあります。
そのデメリット回避のために、録音することを伝えずに録音する方法があります。民事訴訟の場合、原則として証拠能力に制限はありませんので、黙って録音したものも証拠として使えないことはありません。
●証拠化の方法
供述録取書(供述を記録したもの)には、本人の署名捺印が必要です。ワープロ打ちした書類に、捺印するだけは駄目です。供述内容を全て自書するのがいちばんですが、それができない場合には、会社側で供述内容をまとめた書面に自署してもらいます。
後の裁判の際に、怒鳴られた、監禁された、4〜5人に囲まれて詰問口調で自白を迫られたなどという主張をされて供述内容の信用性を争われないように、いつでも出入りが自由な場所で尋問を行って、調書を作成することが重要です。
●物的証拠の確保
本人が保管している会社の所有物を証拠とするために、本人の不在時に机の引出等から確保することも合理的な範囲では許されるでしょう。本人が保管している会社の書類等を秘密裏に閲覧することも同様でしょう。メールについて閲覧が可能であることはすでに説明しました。
しかしながら、私物については、これを本人の承諾なく確保することはできません。ただ、本人の承諾のもと任意の提出を得ることはできます。任意の提出を得て私物を預かる場合、後に会社が勝手に持って行ったなどと言われないように、「今回の件、○○を任意に提出し、会社に対してお預けいたします」という内容の同意書(自書であることが好ましい。少なくとも自署があること)を取っておくべきです。
●パソコンデータの解析
メールの内容は真相解明に非常に役立ちます。ライブドアの堀江氏の事件の場合、東京地検特捜部は、本人たちの供述を取る前にまず家宅捜索に入り、電子メールを確保してその内容が消去されることを回避することを優先する捜査手法を取りました。本人もしくはその関係者から供述を取ることよりも、客観的に証拠となる電子メールの確保を最優先にして強制捜査を行ったのです。
メールの重要性は、社内調査の場合も同様です。この場合、調査対象者によりメールが消去されていることが多々ありますが、解析専門の会社に依頼すればその復元が可能な場合があります。多少の費用がかかってもできるだけ消去データの復元をすることが真相の解明につながることになります。
Ⅲ5つの事例を紹介します
ケース1 セクハラ事件
同僚女性社員の多くが「セクハラはない」という供述を行い、会社が同僚女性社員の供述だからということでこれを全面的に信用してしまったところ、裁判ではこれら女性社員の供述が真実ではないことが判明し、会社が敗訴してしまったという事件です。女性同僚がもっていた被害者に対する妬みの感情が真実ではない供述をした理由のようです。
ケース2 セクハラ事件
1とは逆に、女性社員のセクハラの申し立てを、客観的裏付けもないまま女性の担当役員がそのまま信用してしまった事件です。女性は男性に気にくわないことをされたので、その腹いせに些細なことを大げさに取り上げてセクハラがあったなどという申し立てをしたのですが、女性役員はこうした調査になれていなかった(初めて扱った)のと女性同士ということで安易に同情し、セクハラがあった信用してしまったという事案です。
裁判では、会社側敗訴となりました。
ケース3 セクハラ事件
セクハラがあったと女性社員が男性役員に個人的に相談したものの真剣に対応してくれないとして、監督官庁に不平の申し立てをしました。
この会社は、監督官庁から管理体制ができていないとして注意をうけることになりましたが、セクハラホットラインや、内部通報制度の確立の重要性を認識することになった事件でした。
ケース4 セクハラ事件
セクハラがあったと女性社員からの申し立てがあり、調査の結果女性の言っていることが真実であるという判断に傾きつつあったものの、解析会社に依頼して消去されたメールを復元してもらったところ、その女性の言い分とは違うメールがたくさん出てきたという事案です。
ケース5 横領事件
社員が会社の商品を横流しし、その売却代金を得ていたという事件です。
まず、若い社員が高級車を乗り回しているという内部通報が寄せられました。担当者が事情を聴いたところ、本人は観念し、横領の事実を自白しました。そして、裏付け資料を確保するために、携帯電話や売却代金が振り込まれている預金通帳を任意で提出してもらい、任意で提出した旨の同意書も取って証拠物を確保した上で、刑事告訴を行ったという事件でした。
ケース6 背任事件
このケースは会社の取締役の背任行為が対象になった事件です。
異変に気づいた役員が顧問弁護士に相談し、弁護士マターとして調査が開始されました。ある程度の客観的証拠が揃った段階で、まず直属の部下である部長に対して事情を聴くことにしたところ、1回目の事情聴取には出てきてある程度の供述をしましたが、その後は聴取を拒否するのでこれに応じるよう業務命令を出しましたが、従いませんでした。その後辞表が提出され出社しなくなりました。そのため、当該部長からはほとんど話が聞けなかったという事案です。
やむをえず、その他の社員などから話を聞くなどして間接事実を積み上げ(直接の関与者は当該部長以外にいなかった)、訴訟を提起することができました。業務命令を出すことによって聴取に応じる義務を課すことはできるが、これに応じなくても強制力がないという事案です。