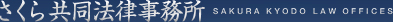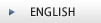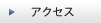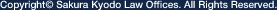2「内部通報後の社内調査の方法」〜社内調査の具体的な進め方〜
目次
Ⅰ 社内調査の特徴と調査協力義務
1 目的
2 強制力の有無
3 協力義務の存否
4 限界
5 真相解明の程度
Ⅱ 社内調査の具体的進め方
第1 事情の聴き取り
第2 物的証拠の確保
第3 パソコンデータの解析
Ⅲ 事例研究
Ⅰ 社内調査の特徴と調査協力義務
1 目的
通報内容に関する事実の真相を解明すること
2 強制力の有無
1) 社内調査には強制力がない。
全てが任意の調査である。
よって、真相の解明ができない、困難。
警察・検察の捜査には、強制力がある。
よって、真相の解明が容易である。
2) そうであろうか。
刑事訴訟法の原則→任意捜査
特に、参考人に対しては、任意捜査
強制捜査を行う場合は、令状主義等厳格な手続きの下でのみ許される。
ただ、任意の聴取に応じなければ逮捕するといって脅すことにより供述を取り、証拠を出させる。
3) 特捜部の捜査
まずは任意捜査
参考人の供述調書の作成と証拠物の任意提出を得る。
調査対象者に対しても、任意で供述調書を作成する。
ほぼ真相を解明、その後、
裁判に耐えうるための最後の証拠固めの部分だけ強制捜査
3 協力義務の存否
1) 契約関係にあることからする権利義務の関係としての強制力はある。
雇用契約及び就業規則その他の社内規定を根拠とする調査に協力する義務あり。
会社の業務命令によって、具体的な協力義務を課す(強制力)。
但し、これに対しては、労働法規やプライバシー権などの権利により対抗される可能性あり。
判例:企業秩序に違反する行為があった場合に、違反行為の内容等を明らかにし、秩序回復に必要な業務上の指示、命令を発し、または違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができるが、その調査や命令は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的なものであり、その方法態様が労働者の人格や自由に対する行き過ぎた支配や拘束ではないことを要する(東京地裁・H14.2.26日経クイック情報電子メール事件)
2) 同じく、会社所有物及び書類の提出義務あり。
3) 会社所有のパソコンに保存された私的メールの調査も可能。
判例1:①社内ネットワークシステムを用いた私用電子メールの送受信につき、日常の社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として用いること、さらに、職務遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合には、外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において発信に用いることも社会通念上許容されている、②従業員が社内ネットワークシステムを用いて電子メールを私的に使用する場合に期待しうるプライバシーの保護の範囲は、通常の電話装置の場合よりも相当程度軽減されることを甘受すべきであり、監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較考量した上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限りプライバシー権の侵害となると解するのが相当(東京地裁・H13.12.3F社Z事業部電子メール事件)
判例2:メールファイルの内容は業務に必要な情報を保存する目的で会社が所有し管理するファイルサーバー上のデータ調査であることから、社会的に許容しうる限界を超えて原告の精神的自由を侵害した違法な行為とは言えない(前記日経クイック情報電子メール事件)
4) 管理規定を置くべき。
① 私用に使うことの禁止、
② モニタリングすることの告知
5) 私有物、プライベートな書類の提出義務はない。
任意で提出してもらうことに問題はない。
6) 私的所有物のパソコン内に保存された業務に関する電子メールに対する調査権があるといったところで、現実に不可能。
手帳類も同様。
4 限界
ただ、警察権力が有する強制力とは別次元である。
義務ではあるが、それを強制はできない。
任意の調査であることにかわりはない。
結局、強制力がないが故の限界はある。
5 真相解明の程度
告訴・告発を目的
懲戒解雇
その余の処分
合意形成による終結
Ⅱ 社内調査の具体的進め方
第1 事情の聴取り
1 通報事実を、通報者サイドから固める。
通報動機を見極める。
通報者も自分の都合の悪いことは隠す(セクハラ等)。
客観的証拠(裏付け)の有無の確認(証拠物、第三者の供述)。
証拠の取得(裏付け)依頼と調査者の協力申し出。
2 第三者の供述を取る。
1) 協力的な者
なぜ協力的かを見極める必要。
安易に信用しない。
派閥間抗争、好き嫌いなど
2) 協力的でない者
説得
調査の重要性、目的の告知
3 共犯的立場の者で、関与の程度が低そうな者から供述を取る。
利益誘導の可否
処分しないこと(軽減すること)を条件に真実を話すよう求める。
警察・検察は、頻繁に使う。
社内処分に関してはあり。但し、事前に権限者との調整の要あり。
4 調査対象者の供述を取る。
1) 真実を供述させるためには
①用意周到な事前準備
事実の経過を時系列で把握
第三者の供述の内容を把握
証拠物の内容を把握
パソコンデータの内容を把握
複数人で聴く
②調査対象者にまずしゃべらせる
調査者がどこまでの事実を把握しているか見極めている
嘘をついていると思う場合は、まず嘘の弁解を徹底的に聞く。
この段階で、供述録取書を取る。
③そして、反対尋問
第三者の供述との矛盾点
証拠物を突きつける
推認部分で議論をしない
証拠の評価で議論しない
説得
利益誘導の可否
2) 録音の適否
言った、言わないを回避
しゃべることもしゃべらなくなる
録音を告げるか。
告げないからといって違法収集証拠になるわけではない。
3) 証拠化の方法
供述録取書には、必ず署名、捺印してもらう。
記名押印にしない。
全て自書してもらう。内容をこちらで用意する場合もある。
4) 後に信用性を争われないために
怒鳴らない。
休憩をはさむ。
自由に出入りできる場で
若い衆をはり付けない
2 物的証拠の確保
1 業務命令による確保
2 不在の時に確保
3 秘密裏に書類、メール等を閲覧
4 私的な物もしくは書類を任意に預かる
5 任意に自宅に同行し、物もしくは書類を預かる
6 携帯電話の確保
7 4,5,6,に関しては、必ず同意書面を取る。自書がベスト。
第3 パソコンデータの解析
1 メールの内容は大変重要
2 消去データも復元可能
3 削除メールは重要な証拠
4 解析会社への依頼
Ⅲ 事例研究
省略
以上
目次
Ⅰ 社内調査の特徴と調査協力義務
1 目的
2 強制力の有無
3 協力義務の存否
4 限界
5 真相解明の程度
Ⅱ 社内調査の具体的進め方
第1 事情の聴き取り
第2 物的証拠の確保
第3 パソコンデータの解析
Ⅲ 事例研究
Ⅰ 社内調査の特徴と調査協力義務
1 目的
通報内容に関する事実の真相を解明すること
2 強制力の有無
1) 社内調査には強制力がない。
全てが任意の調査である。
よって、真相の解明ができない、困難。
警察・検察の捜査には、強制力がある。
よって、真相の解明が容易である。
2) そうであろうか。
刑事訴訟法の原則→任意捜査
特に、参考人に対しては、任意捜査
強制捜査を行う場合は、令状主義等厳格な手続きの下でのみ許される。
ただ、任意の聴取に応じなければ逮捕するといって脅すことにより供述を取り、証拠を出させる。
3) 特捜部の捜査
まずは任意捜査
参考人の供述調書の作成と証拠物の任意提出を得る。
調査対象者に対しても、任意で供述調書を作成する。
ほぼ真相を解明、その後、
裁判に耐えうるための最後の証拠固めの部分だけ強制捜査
3 協力義務の存否
1) 契約関係にあることからする権利義務の関係としての強制力はある。
雇用契約及び就業規則その他の社内規定を根拠とする調査に協力する義務あり。
会社の業務命令によって、具体的な協力義務を課す(強制力)。
但し、これに対しては、労働法規やプライバシー権などの権利により対抗される可能性あり。
判例:企業秩序に違反する行為があった場合に、違反行為の内容等を明らかにし、秩序回復に必要な業務上の指示、命令を発し、または違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができるが、その調査や命令は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的なものであり、その方法態様が労働者の人格や自由に対する行き過ぎた支配や拘束ではないことを要する(東京地裁・H14.2.26日経クイック情報電子メール事件)
2) 同じく、会社所有物及び書類の提出義務あり。
3) 会社所有のパソコンに保存された私的メールの調査も可能。
判例1:①社内ネットワークシステムを用いた私用電子メールの送受信につき、日常の社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として用いること、さらに、職務遂行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合には、外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において発信に用いることも社会通念上許容されている、②従業員が社内ネットワークシステムを用いて電子メールを私的に使用する場合に期待しうるプライバシーの保護の範囲は、通常の電話装置の場合よりも相当程度軽減されることを甘受すべきであり、監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較考量した上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限りプライバシー権の侵害となると解するのが相当(東京地裁・H13.12.3F社Z事業部電子メール事件)
判例2:メールファイルの内容は業務に必要な情報を保存する目的で会社が所有し管理するファイルサーバー上のデータ調査であることから、社会的に許容しうる限界を超えて原告の精神的自由を侵害した違法な行為とは言えない(前記日経クイック情報電子メール事件)
4) 管理規定を置くべき。
① 私用に使うことの禁止、
② モニタリングすることの告知
5) 私有物、プライベートな書類の提出義務はない。
任意で提出してもらうことに問題はない。
6) 私的所有物のパソコン内に保存された業務に関する電子メールに対する調査権があるといったところで、現実に不可能。
手帳類も同様。
4 限界
ただ、警察権力が有する強制力とは別次元である。
義務ではあるが、それを強制はできない。
任意の調査であることにかわりはない。
結局、強制力がないが故の限界はある。
5 真相解明の程度
告訴・告発を目的
懲戒解雇
その余の処分
合意形成による終結
Ⅱ 社内調査の具体的進め方
第1 事情の聴取り
1 通報事実を、通報者サイドから固める。
通報動機を見極める。
通報者も自分の都合の悪いことは隠す(セクハラ等)。
客観的証拠(裏付け)の有無の確認(証拠物、第三者の供述)。
証拠の取得(裏付け)依頼と調査者の協力申し出。
2 第三者の供述を取る。
1) 協力的な者
なぜ協力的かを見極める必要。
安易に信用しない。
派閥間抗争、好き嫌いなど
2) 協力的でない者
説得
調査の重要性、目的の告知
3 共犯的立場の者で、関与の程度が低そうな者から供述を取る。
利益誘導の可否
処分しないこと(軽減すること)を条件に真実を話すよう求める。
警察・検察は、頻繁に使う。
社内処分に関してはあり。但し、事前に権限者との調整の要あり。
4 調査対象者の供述を取る。
1) 真実を供述させるためには
①用意周到な事前準備
事実の経過を時系列で把握
第三者の供述の内容を把握
証拠物の内容を把握
パソコンデータの内容を把握
複数人で聴く
②調査対象者にまずしゃべらせる
調査者がどこまでの事実を把握しているか見極めている
嘘をついていると思う場合は、まず嘘の弁解を徹底的に聞く。
この段階で、供述録取書を取る。
③そして、反対尋問
第三者の供述との矛盾点
証拠物を突きつける
推認部分で議論をしない
証拠の評価で議論しない
説得
利益誘導の可否
2) 録音の適否
言った、言わないを回避
しゃべることもしゃべらなくなる
録音を告げるか。
告げないからといって違法収集証拠になるわけではない。
3) 証拠化の方法
供述録取書には、必ず署名、捺印してもらう。
記名押印にしない。
全て自書してもらう。内容をこちらで用意する場合もある。
4) 後に信用性を争われないために
怒鳴らない。
休憩をはさむ。
自由に出入りできる場で
若い衆をはり付けない
2 物的証拠の確保
1 業務命令による確保
2 不在の時に確保
3 秘密裏に書類、メール等を閲覧
4 私的な物もしくは書類を任意に預かる
5 任意に自宅に同行し、物もしくは書類を預かる
6 携帯電話の確保
7 4,5,6,に関しては、必ず同意書面を取る。自書がベスト。
第3 パソコンデータの解析
1 メールの内容は大変重要
2 消去データも復元可能
3 削除メールは重要な証拠
4 解析会社への依頼
Ⅲ 事例研究
省略
以上