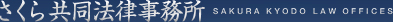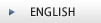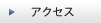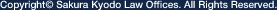1 固定資産評価審査決定取消請求事件
あなたの払っている固定資産税は高くないですか?
「固定資産評価審査決定取消請求事件」において、ほぼ我々の主張が認められて解決した事件がありますので、これについてお話ししたいと思います。
税務訴訟は国を相手にする裁判であって、お上に楯突いても勝訴の見込みが低いと思われがちですが、事案によってはそうでもありません。
この長たらしい名前の事件は、要は、自分(自社)の所有する不動産(本件では建物)に課せられる固定資産税が高すぎる、それは対象となっている不動産の評価額(固定資産評価額)が異常に高いからだという理由で、所有固定資産の価格の評価を見直すことを裁判所に申し立てたという事件です。
バブルの崩壊後こうした税務訴訟がよくありました(市場価格の下落に固定資産評価の改訂が間に合わない)が、不動産バブルとは関係なく、建物の価格の評価の見直しを求め、その申立がほぼ主張通りに認められた案件はあまりないと思います。
この案件の不動産は工場で、数棟の建物から構成されています。町長は、固定資産評価基準に従って、ある年度の本件工場の価格を約4億円と決定し、固定資産課税台帳に登録し、納税通知書を送付しました。
X(建物所有者)は、この価格は、適正な時価(地方税法341条5号)を超えているとして、Y(固定資産評価審査委員会)に対して審査申出を行いました。そうしたところ、YはXの申し出の一部を認め、その価格を約2億9千万円に修正しました。しかし、Xは、修正後の価格もまだ高額にすぎ、適正な時価とはいえないとして、本件税務訴訟を提起したのです。
ところで、固定資産評価額は、市町村がその裁量により算定しているものではなく、総務大臣の告示する「固定資産評価基準」によって算定されています。そして、この基準によれば、建物の再建築費評点数を基礎とし、これに①経過年数に応じる減点補正、②建物の損耗の状況による減点補正、③需給事情による減点補正を行い、建物に評点数を付けます。そして、この評点数に評点一点あたりの価格を乗じて建物の価格を決めます。
ただ、この基準によって算定された価格が、例えば知り合いの不動産鑑定士に鑑定してもらった価格、もしくは近隣での実際の取引価格よりも高額であるからといって、鑑定価格や取引事例での価格まで引き下げるべきだという申出をしても、それが直ちに認められることはありません。なぜなら、不動産の価格の算出方法にもいろいろな考え方や理論があり、その中で上記固定資産評価基準も合理性を有する算出基準であるからです。
そうすると、固定資産評価額を争う方法は、次の二つになります。
第一は、本事案においては、特殊な事情から、上記基準によって価格を算出することに合理性がなく、別な方法(例えば、鑑定士が鑑定価格を算出したときに採用した方法)によるべきだという主張です。第二は、上記基準の合理性を認めた上で、上記①乃至③の減点補正が不十分であるという主張を行うことです。ただ、減点補正を行うべき事情やその割合についても上記基準は詳細な定めをおいていますから、この主張を行う場合でも簡単にこちらの主張が通ることにはなりません。評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別な事情が存することを主張・立証する必要が出てきます。
そこで、本事案では、上記基準の合理性を争うことには精力をそそがず、この基準を前提とした上で減点補正の割合を争うことに注力しました。そして、特に②の減点補正の必要性に関し、各建物ごとに詳細かつ精緻に損耗の事実を立証し、その結果裁判所の納得を得ることができたのです。そして、その後、裁判所の主導により当初の評価額である4億円の半分以下の価格でYと合意をすることができました。ちなみに、固定資産税の税率は、1.4%です。
もちろん、本件建物は工場であり、その稼働状況や構造などから、通常の建物に比較して著しい損耗があったことが、裁判所が我々の主張を認めてくれた大きな理由です。一般の居住用の建物などでこうした主張が認められる余地は少ないと思いますが、程度にもよるということです。
なお、土地についても、土地に関する評価基準の合理性を一応認めながら、そこでの基準となる標準宅地の価格について東京都が用いた価格が客観的な交換価値を上回るという理由で、より低い価格を当てはめて納税者側の主張を認めた判例などもあります。
あなたの払っている固定資産税は高くないですか?
「固定資産評価審査決定取消請求事件」において、ほぼ我々の主張が認められて解決した事件がありますので、これについてお話ししたいと思います。
税務訴訟は国を相手にする裁判であって、お上に楯突いても勝訴の見込みが低いと思われがちですが、事案によってはそうでもありません。
この長たらしい名前の事件は、要は、自分(自社)の所有する不動産(本件では建物)に課せられる固定資産税が高すぎる、それは対象となっている不動産の評価額(固定資産評価額)が異常に高いからだという理由で、所有固定資産の価格の評価を見直すことを裁判所に申し立てたという事件です。
バブルの崩壊後こうした税務訴訟がよくありました(市場価格の下落に固定資産評価の改訂が間に合わない)が、不動産バブルとは関係なく、建物の価格の評価の見直しを求め、その申立がほぼ主張通りに認められた案件はあまりないと思います。
この案件の不動産は工場で、数棟の建物から構成されています。町長は、固定資産評価基準に従って、ある年度の本件工場の価格を約4億円と決定し、固定資産課税台帳に登録し、納税通知書を送付しました。
X(建物所有者)は、この価格は、適正な時価(地方税法341条5号)を超えているとして、Y(固定資産評価審査委員会)に対して審査申出を行いました。そうしたところ、YはXの申し出の一部を認め、その価格を約2億9千万円に修正しました。しかし、Xは、修正後の価格もまだ高額にすぎ、適正な時価とはいえないとして、本件税務訴訟を提起したのです。
ところで、固定資産評価額は、市町村がその裁量により算定しているものではなく、総務大臣の告示する「固定資産評価基準」によって算定されています。そして、この基準によれば、建物の再建築費評点数を基礎とし、これに①経過年数に応じる減点補正、②建物の損耗の状況による減点補正、③需給事情による減点補正を行い、建物に評点数を付けます。そして、この評点数に評点一点あたりの価格を乗じて建物の価格を決めます。
ただ、この基準によって算定された価格が、例えば知り合いの不動産鑑定士に鑑定してもらった価格、もしくは近隣での実際の取引価格よりも高額であるからといって、鑑定価格や取引事例での価格まで引き下げるべきだという申出をしても、それが直ちに認められることはありません。なぜなら、不動産の価格の算出方法にもいろいろな考え方や理論があり、その中で上記固定資産評価基準も合理性を有する算出基準であるからです。
そうすると、固定資産評価額を争う方法は、次の二つになります。
第一は、本事案においては、特殊な事情から、上記基準によって価格を算出することに合理性がなく、別な方法(例えば、鑑定士が鑑定価格を算出したときに採用した方法)によるべきだという主張です。第二は、上記基準の合理性を認めた上で、上記①乃至③の減点補正が不十分であるという主張を行うことです。ただ、減点補正を行うべき事情やその割合についても上記基準は詳細な定めをおいていますから、この主張を行う場合でも簡単にこちらの主張が通ることにはなりません。評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別な事情が存することを主張・立証する必要が出てきます。
そこで、本事案では、上記基準の合理性を争うことには精力をそそがず、この基準を前提とした上で減点補正の割合を争うことに注力しました。そして、特に②の減点補正の必要性に関し、各建物ごとに詳細かつ精緻に損耗の事実を立証し、その結果裁判所の納得を得ることができたのです。そして、その後、裁判所の主導により当初の評価額である4億円の半分以下の価格でYと合意をすることができました。ちなみに、固定資産税の税率は、1.4%です。
もちろん、本件建物は工場であり、その稼働状況や構造などから、通常の建物に比較して著しい損耗があったことが、裁判所が我々の主張を認めてくれた大きな理由です。一般の居住用の建物などでこうした主張が認められる余地は少ないと思いますが、程度にもよるということです。
なお、土地についても、土地に関する評価基準の合理性を一応認めながら、そこでの基準となる標準宅地の価格について東京都が用いた価格が客観的な交換価値を上回るという理由で、より低い価格を当てはめて納税者側の主張を認めた判例などもあります。