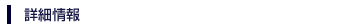
「裁かれるべきは誰か」書評
(ゴルフィスタ2003年10月号掲載)
『法が法として行われているか−法治国家の不幸について』
田野辺 薫
日本は法治国家である。国民はそう思っていて疑わない。凡そそうである。
法治国家の一番の不幸は何か。法律が正しく行われなくなったとき、もっと致命的な不幸は、法律が使用されなくなったときだろう。そうならないため、そのためにも法律は正しく行われなければならない。それは倫理の問題である。
ところが意外に法律は正しく行われていないのだ。法曹の官僚化が進むと、法律は法の精神を失って呪縛だけに陥ってしまう。
石原悟、松井清隆著『裁かれるべきは誰か』(現代人文社刊)は、そんな重いテーマを書いていていろいろと考えることなしに巻を措くことができない本である。しかも2冊だ。
著者2名は弁護士と被告人である。さらにいえばさくら共同法律事務所の所属弁護士とクライアントである。著者に名を並べていないが、西村國彦弁護士も後輩達の応援団長である。弁護料の高い経済事件だけを仕事にしているのかと思っていたさくら共同法律事務所が、社会正義、法治国家の法正義にかかわる重い主題を見逃さなかったこと、2冊の本にして社会に訴えたことに、敬意を表しておきたい。
「やってないことを認めるつもりはありません」
という悲痛だがひどく原始的な叫びからスタートした被告と弁護士のたたかいが、2冊、B6版、計560ページの大部にまで積もり積もったのは、主題の重さもあるが、初審で敗訴したことから始めなければならなかったからだ。上巻は敗戦記である。下巻の最後は逆転無罪だが、その間の記述は精緻をきわめる。不当な取り調べにはげしく怒りながらも、著者は、一方で取調官、検察官、判事の動き、法廷のポジショニングを、まるで見取り図を見るように正確に書いている。法廷小説を書こうと思うほどの人には、大いに参考になる。
この冷静さは、恐らく「やってないことは認められない」という重い戦いを戦い抜くための覚悟と徹底するこころの強さからきている。いきり立つだけでは重い戦いには勝てないのだ。
「上巻」で一番驚いたのは、勾留期間の問題だ。法律では原則として勾留期限は10日間となっている。例外として20日間を認めている。ところが実際は、例外が普通のように行われているのだ。取り調べの警官は、20日を前提にして調べを急ごうとしないし、裁判官は簡単に勾留期間の延長を認める。それどころか、勾留期間を延長までしてていねいに取り調べしたのだから、取り調べ調書は大いに信用できるとして法廷で証拠として採用されやすいというのだから、驚くどころか恐怖さえ感じる。
被告側から見ると、勾留期間が10日から20日に延べること自体が苦痛だ。「早く認めれば、早く出られるゾ」という脅し半分の慫慂(しょうよう)もあるだろう。一種の自白の強要である。それを裁判官は”熱心な取り調べ”と評価するようだ。
本書がタイトルを『裁かれるべきは誰か』とせざるをえなかったのも、その点の指摘を狙ったのだろう。法が法の意図した通りに行われていない。こんな例は、なにもここに書いてある”酩酊えん罪”のような小事件に限らない。もっと大きな重大事件でも行われている。
古い話だが、昭和30年代の終わり頃、松本清張『小説帝銀事件』について、図書新聞に1ページ書評を書く目的で、平沢貞通被告の主任弁護人山田義夫氏と会った。その頃電通通8丁目にあった文藝春秋社地下で、一時間程取材した。つけ加えれば、私は、この取材では、当時巣鴨刑務所に収監されていた平沢被告にも2回面会している。
山田義夫氏は、「平沢は無罪」と明言していた。一方で冤罪が認められることはないだろうともはっきり言っていた。なぜか。警察官から一審、二審の検察、裁判官、最高裁までが誤った判断を維持し続けてきたからだ。認めたら法曹官僚の序列そのものが総くずれになる。法が正しく行われるかどうかよりも、官僚たちの沽券が重要なのである。そして「でも平沢の死刑が執行されることはありませんよ」とも付け加えた。
「裁判でもそうですか。裁判が信用できなければ吾々は何によって守られるのですか」
「自分を守るのは自分だけですよ」
と山田義夫氏は結論づけた。当時と比べると『裁かれるべきは誰か』は最後で無罪を勝ちとった。
平沢貞通は死刑執行されることなく、九十数歳で獄中死した。その後も、小菅の平沢死刑囚の房にはアトリエがつくられていたという噂が絶えなかった。